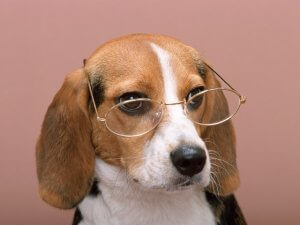書誌_版元ドットコムへのリンク

Mのコメント(位置づけ・批判的思考・つながり)
私は本書と「読んでいない本について堂々と語る方法」を、ほぼ同時期に入手したと思う。両書とも今はあまり見かけなくなった文化人、知識人の香りに満ちた良書と思った。
「もうすぐ絶滅する紙の書物」という表現は、今まさに「書店」の壊滅という我が国の現状を踏まえると切実であるが、驚くべきことに本書の主張は「技術の進歩は避けられない変化をもたらすが、それは必ずしも紙の本の消滅を意味しない。むしろ、新しいメディアの登場は、書物という媒体の持つ独自の価値と永続性を再認識させる機会となる。書物は、その歴史を通じて幾多の破壊と忘却を乗り越えてきたように、これからも技術革命の波を乗り越え、人類の「知と想像の車輪」として存在し続けるであろう」というのである。
「書物という媒体の持つ独自の価値と永続性」には同意するが、そのためにはそれを支えるフィールドが必要であろう。実際、これまでも実際に本を読む人は僅少であり、書店の衰退は、雑誌という媒体の魅力が失せたことに負うところが大きいのではない。とはいえ、私も書店に行く回数が減ったし、もっと深刻なのは、書店で目にした本が電子書籍にあるかもしれないということから(ほとんどある)、買い控えてしまうことである。類似の現象として、電化製品等について現実店舗では商品を見るだけで、購入はAmazonでするということがあったが、Amazonで詐欺商法が横行しているという現状から、現実店舗のオンライン販売が利用されつるあるのではないか。現実店舗である「書店」も、電子書籍を含んで展開するビジネスが考えられないか。
エーコの本は「薔薇の名前」を含めほとんど処分したようである。ジャン=クロード・カリエールについては、「愚論珍論事典」が手元にある。利用方法がむつかしいが。
目次と要旨
目次
- 序文
- 本は死なない
- 耐久メディアほどはかないものはない
- 鶏が道を横切らなくなるのには一世紀かかった
- ワーテルローの戦いの参戦者全員の名前を列挙すること
- 落選者たちの復活戦
- 今日出版される本はいずれもポスト・インキュナビュラである
- 是が非でも私たちのもとに届くことを望んだ書物たち
- 過去についての我々の知識は、馬鹿や間抜けや敵が書いたものに由来している
- 何によっても止められない自己顕示
- 珍説愚説礼讃
- インターネット、あるいは「記憶抹殺刑」の不可能
- 炎による検閲
- 我々が読まなかったすべての本
- 祭壇上のミサ典書、「地獄」にかくまわれた非公開本
- 死んだあと蔵書をどうするか
- 訳者あとがき
- 本の世界はあたたかい 主要著作
要旨
主張
ウンベルト・エーコとジャン=クロード・カリエールによる対談は、技術革新の時代における「本」という存在を多角的に考察し、その永続性と文化における役割を浮き彫りにしている。中心的な論点は、紙の本が車輪やスプーンのように完成された発明品であり、その物理的な堅牢性と柔軟性が、急速に陳腐化するデジタルメディアの儚さとは対照的であるという主張にある。電子書籍の利便性を認めつつも、対談者たちは、五世紀前のインキュナビュラ(初期刊本)が今なお読める一方で、わずか数十年前のデジタル媒体が再生不能になっているという逆説を強調する。
本対談は、文化そのものを「すべてが忘れ去られたのちになお残るもの」と定義し、歴史を通じて行われてきたフィルタリング(選別と篩い落とし)の重要性を説く。インターネットの登場は、このフィルタリング機能を経ない膨大な情報へのアクセスを可能にしたが、それは同時に、共通の文化的基盤を危うくし、あらゆる相互理解を妨げる「六〇億冊の百科事典」を生み出す危険性をはらんでいる。
さらに、対談は真理や傑作の歴史だけでなく、「愚かさ」と「誤り」の探求にも光を当てる。両者は、珍説愚説や疑似科学に関する書物を積極的に収集・研究しており、それらが「半分天才で半分馬鹿」という人間存在の不可分な側面を映し出す重要な鏡であると論じる。この視点は、書物とは単なる知識の集積ではなく、人間の栄光と卑劣さの両方を映し出す、複雑で多層的な存在であることを示唆している。
結論として、技術の進歩は避けられない変化をもたらすが、それは必ずしも紙の本の消滅を意味しない。むしろ、新しいメディアの登場は、書物という媒体の持つ独自の価値と永続性を再認識させる機会となる。書物は、その歴史を通じて幾多の破壊と忘却を乗り越えてきたように、これからも技術革命の波を乗り越え、人類の「知と想像の車輪」として存在し続けるであろう。
第1章: 本の永続性と技術の儚さ
本対談の根幹をなすテーマは、物理的な「本」という媒体の驚異的な永続性と、現代のデジタル技術の急速な陳腐化との対比である。エーコは、本の不変性を次のように断言する。
本は、スプーンやハンマー、鋏はさみと同じようなものです。一度発明したら、それ以上うまく作りようがない。スプーンを今あるスプーンよりよいものにするなんて不可能でしょう。 — ウンベルト・エーコ
この見解は、本が五世紀以上にわたってその基本的な形態と機能を維持してきた完成された発明品であるという信念に基づいている。対照的に、デジタルメディアは絶え間ない変化にさらされている。
1.1 「耐久メディア」の逆説
カリエールは、かつて「耐久メディア」として喧伝された技術がいかに短命であったかを、自身の経験から具体的に詳述する。
- ビデオカセット: 3〜4年で劣化し、使用不能になる。
- 電子カセットとCD-ROM: 1980年代に映像保管の解決策として登場したが、CD-ROMを製造していたアメリカの工場は7年前に閉鎖された。
- DVDと新しいディスク: DVDもやがて陳腐化し、新しい小型ディスクの登場によって再生機器の買い替えが強制される。
この現象は、カリエールが所有する15世紀のインキュナビュラ(1498年刊『時禱書』)が、5世紀以上経過した現在でも容易に解読可能であるという事実によって、より一層際立たされる。
五世紀も前に印刷された文書を私たちは読むことができるんです。しかし電子カセットや、ほんの数年前に使っていた古いCD|ROMは、いまや読むことも観ることもできません。地下倉に旧式のコンピューターを保管しているんなら話は別ですが。 — ジャン=クロード・カリエール
1.2 電子書籍の功罪
対談者たちは電子書籍の利便性を否定しない。膨大な文書(例:裁判の証拠書類)の持ち運びや、オンラインでの稀覯書へのアクセス(例:ミーニュの『ラテン教父叢書』)といった利点は大きい。しかし、以下の懸念も表明されている。
- 身体的負担: コンピューター画面での長時間の読書は、深刻な眼精疲労を引き起こす。
- 環境的制約: 電力を必要とするため、風呂場やベッドでの読書には適さない。
- 愛着の喪失: 書き込みや変色といった、個人の読書体験の物理的な痕跡が失われる。エーコは、自身が書き込みをしたジルソンの『中世の哲学』の古い版が物理的に崩壊していくことを嘆く。
最終的に、本は技術の波に乗り越えられるという楽観的な見通しが示される。紙の本は、電気がなくとも太陽光や蝋燭の灯りで読むことができ、その単純さこそが究極の強みである。
第2章: 文化、記憶、そしてフィルタリングの力学
本対談では、文化とは単なる知識の蓄積ではなく、選択と忘却のダイナミックなプロセスであるという視点が提示される。
2.1 文化の定義とフィルタリング
文化は、膨大な創造物の中から何かが失われ、何かが残るという絶え間ないフィルタリングの結果として形成される。
文化とはすべてが忘れ去られたのちになお残るものにほかならない、ということです。 — ジャン=フィリップ・ド・トナック(序文より)
このプロセスは恣意的かつ偶然的であり、我々が今日「傑作」として知るものが、必ずしもその時代で最高のものであったとは限らない。
- ギリシャ悲劇の例: アリストテレスは『詩学』で当時の代表的な悲劇詩人を列挙しているが、今日「三大悲劇詩人」とされるアイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデスの名前には触れていない。我々が失った作品は、現存するものより優れていた可能性がある。
- 映画の例: 初期の映画フィルムは芸術とは見なされず、多くが廃棄された。アメリカでシネマテークが設立されたのは1970年代になってからである。
2.2 記憶の二重機能
記憶は、個人であれ集団であれ、二つの相反する機能を持つ。
- 保存: 重要なデータを保持する。
- 忘却: 不要な情報を整理し、脳内の混乱を避ける。
すべてを記憶してしまう文化は、ボルヘスの小説に登場する「記憶の人フネス」のように、文化の対極にあるものとして描かれる。文化は、何を残し、何を捨てるかを選別することで機能する。
2.3 インターネットがもたらす課題
インターネットは、この伝統的なフィルタリングのメカニズムを根底から覆す可能性を秘めている。
- 未精製の情報: インターネットは、出典の保証も権威づけもない玉石混淆の情報を提供する。
- フィルタリングの個人化: かつて文化が担っていたフィルタリング機能を、個人が自身の頭で行わなければならなくなる。
- 共通基盤の喪失: これにより、エーコが「六〇億冊の百科事典」と呼ぶ状況が生まれかねない。共通の知識基盤がなければ、いかなる対話も相互理解も困難になる。
この課題に対し、教育現場では、複数の情報源を比較検討させ、インターネットに対する批評感覚を養う訓練が不可欠であると提言されている。
第3章: 「愚かさ」と「誤り」の礼讃
対談の最も独創的な部分の一つは、一般的に価値がないとされる「愚かさ(珍説愚説)」や「誤り」を積極的に評価する視点である。
3.1 収集のテーマとしての「愚かさ」
両者は、単なる美しさや真実だけでなく、人間の愚かさや誤りを体現した書物を熱心に収集している。
- ウンベルト・エーコ: 彼のコレクションは「神秘学と疑似科学」をテーマとし、真理であったプトレマイオスの天動説の本は所蔵するが、正しかったガリレイの本は所蔵しない。彼は誤りや贋物に「どうしようもなく惹かれる」と語る。
- ジャン=クロード・カリエール: ギィ・ベシュテルと共著で『珍説愚説辞典』を執筆。「フロベールがこよなく愛した珍説愚説は、もっとずっとずっと広く蔓延しているのはもちろんのこと、もっと豊饒で、もっと示唆に富み、ある意味では的確なものに思えた」と述べる。
3.2 人間存在へのオマージュ
愚かさの探求は、単なる知的好奇心にとどまらない。それは、人間という存在そのものへの深い洞察に基づいている。
したがって、愚かしさをテーマに語ろうとは言ったものの、これは、半分天才で半分馬鹿という、この人間という存在に対するオマージュなんです。 — ウンベルト・エーコ
書物は、人類の偉大な達成だけでなく、その卑劣さや愚行をも忠実に反映する鏡であり、その両側面を評価することではじめて、人間を誠実に理解できるとされる。
3.3 愚説の具体例
対談では、歴史上の数々の珍説愚説が紹介され、それらが当時の社会や精神性をいかに的確に映し出しているかが示される。
- ナショナリスト言語学: 自国の言語こそアダムが話した原初の言葉であると主張する様々な学者たち(例:アントワープ方言が一次言語であるとしたゴロピウス・ベカヌス)。
- ピラミッド学: クフ王のピラミッドにあらゆる宇宙の寸法が含まれているとする説。
- 人種差別的言説: 「ドイツ民族の糞便過多(ポリケジー)」を論じたエドガール・ベリヨンや、ユダヤ人に関する様々な迷信。
これらの愚かな言説は、しばしば科学的な装いをまとい、その時代の「真実」として受け入れられていた。その歴史を学ぶことは、現代における我々自身の盲点を省みる上で極めて重要である。
第4章: 書物の破壊と生存の歴史
書物の歴史は、創造の歴史であると同時に、絶え間ない破壊の歴史でもある。この「ビブリオコースト(書物大量焼却)」は、様々な要因によって引き起こされてきた。
4.1 破壊の要因
- 検閲と異端審問: 宗教的・政治的権力が、自らにとって不都合な思想を抹殺するために書物を破壊した。
- 火災: 中世の図書館や大聖堂は木造が多く、偶発的な火災によって膨大な書物が失われた。『薔薇の名前』の図書館の炎上は、この時代におけるありふれた事件であった。
- 無知と怠慢: コミック・ストリップの原画や初期の映画フィルムが価値を認識されずに廃棄されたように、文化的価値への無理解が多くの損失を生んだ。
- 意図的な文化破壊: スペイン人による新大陸のコデックス焼却や、ナチスによる焚書は、単なる検閲を超え、ある文化全体を抹殺しようとする試みであった。
4.2 生存の戦略
破壊の脅威に対し、人類は書物を守るための様々な戦略を発展させてきた。
- 修道院の役割: ローマ帝国末期、蛮族の侵略から書物を守るため、修道院が安全な保管場所となった。しかしこれは同時に、何を守り、何を捨てるかという選別(フィルタリング)の始まりでもあった。
- 個人の抵抗: ベルナルディーノ・デ・サアグンのように、公式な破壊命令に背き、ひそかに書物を複写して後世に伝えた人物もいた。
- 奇跡的な発見: 中国・敦煌の洞窟から、千年間封印されていた数万点の写本が発見された例のように、偶然によって失われたはずの知が現代に蘇ることもある。
4.3 作家自身による破壊
興味深いことに、破壊への衝動は外部からだけでなく、創作者自身の内部からも生じることがある。
- ウェルギリウス: 臨終の床で『アエネーイス』を燃やすよう命じたとされる。
- フランツ・カフカ: 死後に自身の作品をすべて焼却するよう友人に依頼した。
- アルチュール・ランボー: 『地獄の一季節』を自ら破棄しようとした。
この破壊願望は、作品への不満だけでなく、自らの死とともに世界の一部を道連れにしたいという根源的な衝動の表れかもしれない。
第5章: 技術革新と人間性の変容
対談は、技術が人間の知覚、習慣、さらには社会構造に与える影響について深く考察している。
5.1 新技術への適応と「現在の消失」
現代の技術革新は、その速度において過去とは比較にならないほど速く、人間は絶え間ない適応を強いられている。
- 思考習慣の再編: 2年ごとのコンピュータ買い替えのように、技術の更新速度は人間の学習速度を超えつつある。
- 現在の不安定さ: かつて30年続いた流行が30日で終わるように、「現在」は縮小し、常に未来に備える努力を強いられる不安定な時間となっている。
- 学習の終焉の終焉: かつては青年期に得た知識が生涯有効であったが、現代では知識の更新を怠れば職を失う。「終身学習刑」が宣告されている。
5.2 技術による言語の創造
新しい技術は、それ自体が新しい「言語」や表現方法を生み出す。
- 映画言語の進化: 固定カメラによる演劇の撮影から始まった映画は、カメラの移動、編集(モンタージュ)、カットバックといった技法を獲得し、独自の言語を発展させた。観客もまた、この新しい言語を学習する必要があった。
- ビデオクリップの影響: アクション映画では、3秒以上続くショットがないという約束事が生まれるなど、技術がアクションそのものを生み出している。
5.3 古い夢想の具現化
一方で、最新技術の多くは、人類が古くから抱いてきた夢や神話の実現であるとも指摘される。
- ウェルギリウスと仮想空間: 『アエネーイス』における冥界降りの描写は、過去と未来、存在と無が共存する現代の仮想空間を先取りしている。
- 『マハーバーラタ』と科学技術: 腹を叩いて鉄の玉を産み、それを100個に割って瓶に入れることで100人の息子を得る王妃の物語は、人工授精やクローニングの原型と見なせる。
これらの例は、技術的進歩が必ずしも直線的なものではなく、人間の根源的な想像力と深く結びついていることを示している。
第6章: 愛書趣味の世界:収集という情熱
対談者であるエーコとカリエールは、共に熱心な古書収集家であり、その情熱と哲学が対談に深みを与えている。
6.1 収集の動機と喜び
古書収集の魅力は多岐にわたる。
- 物理的な美しさ: 装幀、活字、挿絵、紙質など、本そのものが持つ美的価値。
- 希少性: 発行部数の少なさや、市場での入手の困難さ。
- 伝来: かつての所有者の痕跡(書き込み、蔵書印など)が本に付与する歴史的価値。
- テーマ性: 特定の主題(エーコの疑似科学、カリエールの17世紀フランス大衆文学など)に沿ってコレクションを構築する知的探求。
6.2 収集行為の本質
真の収集家にとって、喜びの核心は所有そのものよりも探求のプロセスにある。
真の収集家は書物の所有より探求に興味を持つものです。真の狩人にとっては狩猟という行為がまず興味の中心であって、仕留めた獲物を調理したり食べたりというのは二次的な興味でしかない、それと同じですね。 — ウンベルト・エーコ
このため、コレクションが完成すると、それを売却したり図書館に寄贈したりする収集家も少なくない。ブラジルの大収集家ジョゼ・ミンドリンが、苦労して手に入れた稀覯書を帰りの飛行機に置き忘れても「正直何とも思わなかった」という逸話は、この本質を象徴している。
6.3 古書市場の現実
- 価格の高騰: 投資目的の購入者の参入により、近年、オークションでの価格は不当に吊り上げられる傾向にある。
- 市場からの消失: 収集家が亡くなると、そのコレクションはしばしば公的な図書館に寄贈され、二度と市場には戻ってこない。これにより、稀覯書はますます希少になり、価格が上昇する。
- 掘り出し物の逸話: それでもなお、言語の壁(アメリカでのラテン語本)や分類ミス(神学部門のオカルト本)などを突くことで、安価で貴重な本を手に入れる幸運も存在する。
古書収集は、単なる趣味を超え、歴史との対話であり、知的な冒険であると同時に、市場の力学と渡り合うゲームでもある。
第7章: 読まれざる書物と存在しない著者
対談は、我々と書物との関係について、常識を覆すような provocative な問いを投げかける。
7.1 読んでいない本について語る
膨大な数の書物が存在する現代において、すべての本を読むことは不可能である。ピエール・バイヤールの議論を引き合いに出し、読んでいない本について語ることは正当であり、また不可避であると論じられる。
- 知識の伝達経路: 我々は本を直接読まなくとも、他の本での引用や批評、会話などを通じて、その内容や位置づけについてのかなりの知識を得ている。
- 書棚の機能: 自宅の書棚は、読んだ本の記録である以上に、「来週読まなければならない本」や「読んでもいい本」を置く場所であり、一種の「知識の保証」として機能する。
7.2 傑作の形成プロセス
ある作品が「傑作」となるのは、その作品が本来持つ質だけでなく、後世の無数の解釈が積み重なることによってである。
我々はシェイクスペリアを、シェイクスペリアが書いたようには読みません。したがって我々のシェイクスペピアは、書かれた当時に読まれたシェイクスペリアよりずっと豊かなんです。 — ウンベルト・エーコ
- 解釈の吸収: 作品が自ら喚起した解釈を吸収することで、その個性はより強くなる。知られざる傑作とは、充分に読まれ、解釈される機会のなかった作品である。
- 後世からの影響: カフカを読むことでセルバンテスの読み方が変わるように、後の作品が先行する作品に影響を与えることもある。
7.3 存在しない著者の創造
対談の最後には、エーコ自身が関わった、存在しない作家ミロ・テメスヴァルをでっち上げた逸話が披露される。フランクフルトのブックフェアで、出版界の馬鹿げた傾向を揶揄するために流されたこの冗談は、瞬く間に業界に広まり、ついにはある出版社が「海外出版権を買った」と宣言するに至った。エーコはその後も自身の著作でテメスヴァルを引用し続け、この架空の作家に現実世界での生命を与えた。このエピソードは、書物と名声の世界がいかに虚構と現実の境界線上で成り立っているかをユーモラスに示している。