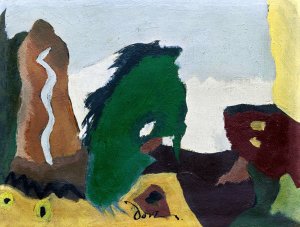Mのコメント
「問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する:安藤昭子」は、故松岡正剛のスキーム(例えば「知の編集工学」)と重なる部分があるが、文化・教養に関わる問題をきちんと整理していて、格好いいし、応用範囲も広いので参考になる。
CNoteのまとめ
ところで本書について、作者が重要だとと考えている点について、GNoteに5点挙げてもらった。以下の回答であった。
•問いを生み出す力
「わからない」を「わかりたい」と思ったときに、「未知」は「問い」として動き出す。
「問う」自由を自分自身の手もとに取り戻すつもりで編集力を駆動すれば、まどろみから目覚める赤い薬は、日常のいたるところに落ちている。
自分の内側から次々と泡立つように湧き出てくる小さな問いの群れが、「読み」を加速させる。
本を媒介に引き出される誰かの言葉にはっとして、自分の内側から思いも寄らない「問い」が湧き出てくる。
「なぜ、そうなっているのか?」「それはそもそもなんなのか?」、ちょっと立ち止まって考える習慣を持ってみると、そこかしこの解像度が上がっていく。
•編集力。
「私」とはなにかを定義するよりも、「私は○○○な×××である」の「○○○」や「×××」を次々と自分の中に発見していくほうがいい。
新しく引き出されたペンネーム(ニューワード)同士は、必ずしも整合性のとれた情報ではないはずなので、自分の奥に隠れている思わぬ「ギャップ」も発見するはずだ。
「言い換える力」もしくは「連想力」は、こうした編集のバッファを意図的につくっていく上で大事な役割を担う。
編集工学は「伏せて開ける」ことを重視する。
自分自身の想像力を主役にして、配役を決め直せばいい。そのためにどうしても必要なのが、情報を主体的に扱う「編集力」なのだ。
•自己認識
「私」という強固な枠組みをゆるませる必要がある。
物事を大きく変化させ動かしていくのは、常に落差やズレ、矛盾や葛藤だ。
「たくさんの私」を書き出す。
昨今の炎上現象は、社会全体がこうした主語の動向ばかりを気にしすぎていることに起因しているようにも思う。
自分ではない何者かが強力に決定していく境界を、私たちは自分自身で選択し設定し直す必要がある。少なくとも、そのことに自覚的であるべきだ。
自分の注意のカーソルに自覚的になる際に、デノテーションとコノテーションの両方に意識を向けるようにすると、見過ごしている疑問や違和感にも出会えるようになる。
•他者との関係における自己
「主体としての木こりが対象としての木を切っている」という認識をいったん捨てよ。
京都の人は、客人にそろそろお暇いとま願いたいときに「ぶぶ漬け(お茶漬け)でもどうどす?」と言う。
それぞれのメガネをかけ替えながら、いつもの通りを歩いてみよう。
人が世界にあるものを原材料にして活動しているのではなく、世界の側が人間を原材料にして自転し始めているというのだ。
いつもと違うことを考え話す場。
どんな情報も、私自身も、この世のあらゆる事柄も、無数の関連する情報を引き連れながらなんらかの文脈の上にある。誰もがこの世界への途中からの参加者なのだ。
•学習と経験
どんな言説も、自分の想像力と交わらないと、理解することも解釈することもできない。
「~といえば○○」といった表層的な連想からくるステレオタイプ(典型)、「○○とはつまり~」と事象の概観を捉えるプロトタイプ(類型)、「○○はそもそも~」と起源をたどるアーキタイプ(原型)だ。
世界中の未知を運ぶ本という情報デバイスと、いくつもの文脈を内包しうるテキストは、どんな「読み」も無限に引き受ける器になる。
何かを「まっさらな目」で見るためには、そのことを一度「アンラーン」 する必要がある。
私たちは必ずや何らかの枠組みを通して物事を理解している。
人が学習Ⅱから学習Ⅲへ移行するのは、そう簡単なことではない。
古い問いを決然と拒絶し、新たな問いを絶え間なく生み出す力が、そのまま生きる力となる。
私としては、やっと本の内容の要約、詳細目次を作成し、投稿することができる地平に届いたことがとても嬉しい。でもそれは初歩の初歩で、今後CNoteとの対話で、本からどのような知見を引き出すことができるか、楽しみで仕方ない。
<問いの編集力>の要約と目次
書誌:問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する: 安藤昭子( ディスカヴァー・トゥエンティワン)
各章の要約
著者は、人がなぜ疑問を抱くのか、その疑問を持続させるものは何か、そして「問い」がいかに知的営みやエネルギーになりうるのかを考察します。「問い」は、人々の知性や経験、勇気を反映し、自分自身や世界を大きく動かす可能性を秘めていると著者は述べています。本書では、問いが生まれるプロセスを4つのフェーズに分け、それぞれの段階で必要な思考や行動について解説しています。最終的には、「問い」を通じて世界を再解釈し、新たな価値を創造することを目指します
はじめに ――なぜ「問い」を「問う」のか
「科学道100冊」での経験を基に、「疑問のはじまり」という問いに向き合った著者の問題意識が述べられています。教育現場やビジネスの現場で「問い方」が課題となっている現状を指摘し、「問い」が個人の知性や経験、世界を動かすエネルギーになりうることを強調しています。子どもから大人まで共通の課題として「いかに問うか」を捉え、「問い」の発生現場の謎を解き明かすことを本書の目的としています。
第1章 Loosening 「問い」の土壌をほぐす
この章では、「問い」を生み出すための内面の準備について解説します。「私」という固定概念から自由になり、多様な視点を持つことの重要性を説いています。自己を柔らかくほぐし、固定された認識を解放することで、新たな発想が生まれる土壌を耕すことを目指します。
具体的には、「たくさんの私」を解放する練習問題が紹介されています。これは、「私は○○○な×××である」という構文を用いて、自身の属性や特徴を列挙することで、自己認識を多角化する試みです。また、主語的な自己だけでなく、述語的な自己にも目を向けることで、より多面的な自己理解を促します。
さらに、主体と客体を分離する二項対立的な世界観から脱却し、相互作用的な視点を持つことの重要性を説いています。システム思考を取り入れ、自己と環境の関わりを意識することで、新たな気づきや発想が生まれる可能性を示唆しています。
第2章 Remixing 「問い」のタネを集める
この章では、多様な情報に触れ、視点を切り替えることで「問い」のタネを集める方法を解説します。固定的な見方にとらわれず、多角的な視点を取り入れることで、新たな発見を促すことを目指します。
具体的には、デノテーション(直接的な意味)とコノテーション(連想的な意味)の両方を意識することで、情報の多面性を捉える練習が紹介されています。また、普段とは異なる「メガネ」をかけて物事を観察することで、新たな視点を発見する試みが提案されています。
偶然性や異質な要素を積極的に取り込むことの重要性も強調されています。セレンディピティ(予期せぬ発見)を意識し、偶然の出会いから新たな発想を生み出すことを奨励しています。
第3章 Emerging 「問い」を発芽させる
この章では、集めた「問い」のタネを発芽させ、具体的な「問い」として意識化する方法を解説します。現代社会における情報過多や監視資本主義の問題点を指摘し、本当に知りたいことを見つける難しさを指摘しています。
質の高い「未知」に出会うために、書物を活用することを提案しています。書物を単なる知識のインプット手段としてではなく、思考や想像力を触発する装置として捉え、著者と読者のイマジネーションが混ざり合う場を設けることの重要性を説いています。
具体的には、「探究型読書」という読書法を紹介しています。これは、本の内容を理解することよりも、本を手がかりにして思考を進めることを重視するアプローチです。読者の問題意識や仮説をフィルターにして本から情報をすくい上げ、それによってまた自分の仮説を進めていくというサイクルを回すことを目指します。
第4章 Discovering 「問い」が結像する
この章では、「問い」を深掘りし、明確な形として結像させる方法を解説します。過去の知識や経験にとらわれず、新たな視点から物事を捉え直す「アンラーン」の重要性を説いています。
アンラーンを促進するために、物事の起源や本質を問い直すことを提案しています。アーキタイプ(原型)に着目し、固定観念にとらわれずに物事を捉えることで、新たな発見を促します。また、「なぜなに変換」を推奨し、日常的な事柄に対しても根本的な疑問を持つことで、思考を深めることを目指します。
アブダクション(仮説形成)という推論方法を紹介し、不確実な情報から新たな仮説を生み出す思考プロセスを解説しています。シャーロック・ホームズのような名探偵の思考を例に、直感やひらめきを活用しながら、論理的な思考だけではたどり着けない結論に到達する可能性を示唆しています。
第5章 「内発する問い」が世界を動かす
この章では、「問い」を社会に発信し、世界を動かす力に変える方法を考察します。「問いのパラドックス」という難題に触れ、「暗黙知」の重要性を説いています。
グレゴリー・ベイトソンの学習階型論を紹介し、学習のプロセスを深く理解することで、より高次の視点から「問い」を捉えることができることを示唆しています。
また、システム思考の重要性を改めて強調し、自己と環境の相互作用の中で「問い」を捉えることの重要性を説いています。
おわりに ――「問う人」として
「古い問いを拒絶する」勇気を持つことの重要性を説いています。既存の価値観や常識にとらわれず、自らの内なる声に耳を傾け、真に問うべき問いを探求することの重要性を強調しています。
全体の要約
本書は、「問いの編集力」をテーマに、「問い」をどのように生み出し、活用していくかを探求する書籍です。「問い」は、人々の知性や経験、勇気を反映し、自分自身や世界を大きく動かす可能性を秘めていると著者は述べています。本書では、問いが生まれるプロセスをLoosening(土壌をほぐす)、Remixing(タネを集める)、Emerging(発芽させる)、Discovering(結像する)という4つのフェーズに分け、それぞれの段階で必要な思考や行動について解説しています。最終的には、「内発する問い」を通じて世界を再解釈し、新たな価値を創造することを目指します。また、アブダクションやアンラーンといった思考法や、書物の活用法、学習階型論など、様々なツールやフレームワークを紹介しながら、「問い」を深掘りし、社会に発信していくための具体的な方法を提示しています。
詳細目次
はじめに ――なぜ「問い」を「問う」のか
第1章 Loosening 「問い」の土壌をほぐす
「私」から自由になる 内面の準備
想像力の土壌
「たくさんの私」を解き放とう
主語より述語に強くなる
インターフェイスを柔らかく 接面の準備
「私」と「世界」が接するところ
つながり合う世界
アフォーダンスとマイクロスリップ
縁側が必要だ 境界の準備
ウチソト感覚
「間」をゆるませる
第2章 Remixing 「問い」のタネを集める
見方が変われば、世界が変わる 意味の発見
デノテーション、コノテーション、アテンション!
アレに見えてしょうがない
フィルター越しの世界
情報は多面的 視点の切り替え
連想が止まらない
「地と図」のマジック
偶然を必然に 異質の取り込み
偶然性とセレンディピティ
問いは驚きに始まる
第3章 Emerging 「問い」を発芽させる
見えない壁に穴をあける 未知との遭遇
「問い」が奪われている?
子どもは40000回質問する
未知を焚べる
無数の世界に誘われる 触発装置としての書物
書物という情報デバイス
思考の縁側を確保する
コラム 「読み」と「問い」の連鎖を起こす「探究型読書」のすすめ
読書は「略図的原型」で進む
読む力、問う力
リンキングネットワークの拡張へ 関係の発見
言葉の網目と問いの網目
松岡正剛の読書風景
才能を引き出す場のダイナミズム「連れん」
コラム 問いと本と対話を創発する一畳ライブラリー「ほんのれん」
第4章 Discovering 「問い」が結像する
アンラーンの探索 世界の再解釈
「私」の源に会いに行く
物語の力
他にありえたかもしれない世界 内発する問い
「なぜなに変換」のススメ
途中からの参加者として
仮説で突破する 新たな文脈へ
「あてずっぽう」で突破する探究の論理学「アブダクション」
アブダクティブ・ライティング(Abductive Writing)
第5章 「内発する問い」が世界を動かす
「問う」とはつまり何をしていることなのか
まだ出現していない可能性へのアクセス
「問いのパラドックス」を超えて
暗黙知と創発知
世界像が変容する ベイトソンの「学習Ⅲ」へ
まだ見ぬ世界への扉を開く
学びの相転移:ベイトソンの学習階型論
吉と出るか凶と出るか?! 「ダブルバインド」の威力
暴走する世界の中で
循環するフィードバック
流れに「句読点」を打つ問い
自己の時を刻む
おわりに ――「問う人」として
参考文献