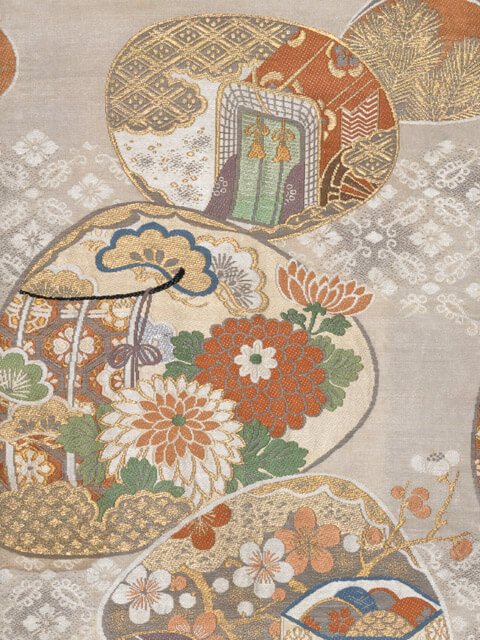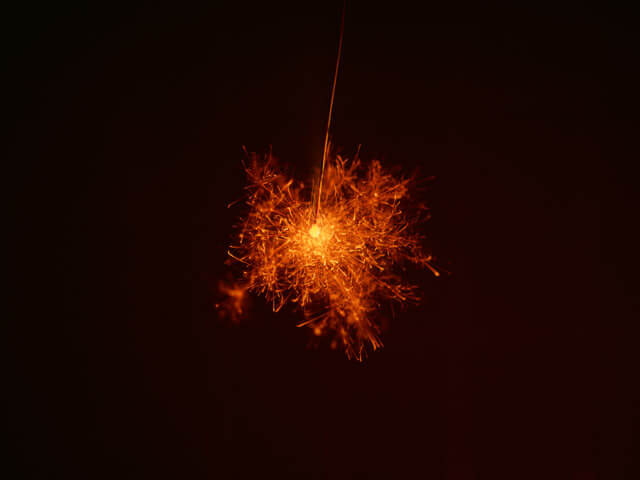-

迷路としてのAIサービス:個人の知的生産と業務の自動化・効率化を阻むもの
導入 私の生成AIの利用は、NotebookLMやDeepReseachを使用しての長文の要約と検索・調査が中心であった。しかしそれでは用途が限られるので、ChatGPTが何に使えるのか、どのように使うのか、あれこれ見繕っているうちに、Geminiも目に入ってきた。GeminiはAIチャットとして利用する限りは、ChatGPTと大同小異だが、Googleは、Chrome、Drive、... -

フランスの高校生が学んでいる哲学の教科書_を読む
フランスの高校生が学んでいる哲学の教科書_への道標 書誌_フランスの高校生が学んでいる哲学の教科書:シャルル・ペパン 短い紹介と大目次 短い紹介 本書は、伝統的な知の探求にとどまらず、哲学を「生きるための教科書」として捉え直し、思考を喜びや力と結びつけることを目指している。本書は、自己が独立しているか他者との関係で定義... -

フランスの「哲学とは何か」:バカロレアの哲学試験
バカロレアの哲学試験をめぐって 哲学の「本_を読む」 「「本_を読む」(本が読めない)問題への対応_試論」で、「国語問題」と「記号接地問題」から、言語空間(文字テキスト)を眺めてみた。次は実際の本に向かってみよう。まずは「哲学」の本だ。私は、哲学は、概念(観念)とその周辺を整序するツールだと思う。したがって、「国語問... -

小休止して整理しよう
小休止して整理しよう サイト修正のためにやっている作業が複雑多岐になり少し混乱してきたので、小休止して整理しよう。 原動力 今回のサイト修正の原動力は、「NotebookLM」である。これで長文のPDFやテキストの内容の要約ができる。今は、これまでに言及した本について取り急ぎ「目次」に加えて「要約」を加え、全体を整備する段階なので... -

「本_を読む」(本が読めない)問題への対応_試論
「本_を読む」(本が読めない)問題とは? 私の手元にはデジタルで9000冊以上の本があるが(語学書、若干の漫画も含む。)、この「本が読めない」。1日1冊目を通しても20年以上かかる量から任意の本を選択することも大変だし、そもそもデジタル本は目を通すのは簡単だが「読みにくい」。読みにくい本の大部分は、文・パラグラフや章... -

大人のための国語ゼミ_を読む
大人のための国語ゼミ_への道標 書誌_大人のための国語ゼミ:野矢茂樹 短い紹介と大目次 短い紹介 本書は、子どもではなく、国語の授業から離れた大人たちを対象とした、実用的な文章力を鍛えるための指南書である。本書の主な目的は、日常生活や仕事で必要とされる「普段使いの日本語」の運用能力を磨くことにあり、読み手が「国語の学び... -

難解な本を読む技術_を読む
難解な本を読む技術_への道標 書誌_難解な本を読む技術 (光文社新書):高田明典 短い紹介と大目次 短い紹介 本書は、難解な本を理解するための「読書の技術」を、受動的ではなく能動的な営みとしての体系的なスキルとして捉えている。著者によれば、読書とは知識や思想を自分のものとする能動的な行為であり、その技術は「同化読み」と「批... -

「文」とは何か_を読む
「文」とは何か_への道標 書誌_「文」とは何か 愉しい日本語文法のはなし:橋本陽介 短い紹介と大目次 短い紹介 本書は、日本語の「文法」という主題を、単なる退屈な学問ではなく、人間の本質に迫る「知的なエンターテインメント」として捉え直すことを提案している。特に、学校文法が「文」の基本を「主語と述語」とし、その分析が主に古... -

賢い人の秘密_を読む
賢い人の秘密_への道標 書誌_賢い人の秘密 アリストテレスが史上最も偉大な王に教えた「6つの知恵」:レイグ・アダムス 短い紹介と大目次 短い紹介 本書は、真の知性とは、知識の量ではなく「どう思考するか」にあると主張している。導入部では、生きていくために学ぶ炭鉱夫の娘と、知的好奇心から難解な書物を読むロンドンのビジネスマン... -

相対化する知性_を読む
相対化する知性_への道標 書誌_相対化する知性-人工知能が世界の見方をどう変えるのか:西山 圭太; 松尾 豊; 小林 慶一郎 短い紹介と大目次 短い紹介 本書は、人工知能(AI)の出現と社会実装が人間の知識体系や社会の価値観にどのような影響を与えるかを多角的に考察する。三部構成で、第1部はAIの爆発的進展の核であるディープラーニング...
問いは世界を創造する_生成AIと共に問題を見極め解決する
下に↓過去の記事のスライダー↓お薦めメニュー↓最新ブログの抜粋があります