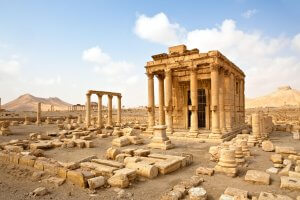人類の社会性の進化_への道標
書誌_人類の社会性の進化 (上)(下)
人類の社会性の進化 (上)「社会」の学としての霊長類学:山極寿一; 本郷峻(Amazonにリンク)
人類の社会性の進化 (下)共感社会と家族の過去、現在、未来:山極寿一; 本郷峻(Amazonにリンク)
※アイカードブックという[カードタイトル(カード番号)+百五十字前後の本文+参考文献(書籍、論文、Web記事他)+註]で構成された「知識カード」であり、Amazonにしかない可能性がある。
短い紹介と大目次
短い紹介
(上)でまず日本と欧米の霊長類学の歩みを概観し、霊長類の社会性が食物と性の二つの主要因によって形作られるという視点から、ニホンザル社会の地域差や、ゴリラとチンパンジーの共存戦略を詳細に分析する。人類の進化においては、高い知性ではなく直立二足歩行こそが根源的な特徴であり、厳しいサバンナ環境への適応として、類人猿とは異なる積極的な食物分配が進化し、これが人類の社会構造と脳の拡大を促したとしている。
(下)では、特に、人類の歴史の大部分は暴力とは無縁で、むしろ食肉目などの被食者として進化してきたという「狩猟仮説」を否定する視点が強調されている。また、ニホンザルに代表される旧世界ザルの直線的順位に基づく攻撃交渉に対し、類人猿やヒトは対面コミュニケーションを通じて社会関係を調整するという、種による大きな違いを解説している。さらに、人類固有の幼年期と青年期を含む特殊な生活史が、多産と大脳化、そして食物の共同保育と食物分配から生じた家族構造と共感能力の誕生に深く関わっていることを示し、、農耕の開始とそれに伴う定住と所有意識の強化が、現代社会に蔓延する暴力の起源となった経緯、そして現代のコミュニケーション変容が家族と社会の未来に与える影響について考察している。
大目次
- 霊長類学の歩んできた道
- ニホンザルの社会とは
- 霊長類進化の舞台
- 食と性が社会性をつくる
- 暴力と社会
- 生活史戦略の進化
- 心の理論とコミュニケーション革命
- 家族の変容とヒト社会の未来
一口コメント
人類の社会がどのように形成されてきたのかの「知識マップ」として優れている。
要約と詳細目次
人類の社会性の進化:山極寿一氏,本郷峻
要旨
本書は、霊長類学の観点から人類の社会性の起源、進化、現代的課題を統合的に分析したものである。主要な洞察は以下の通りである。
- 霊長類学の革新と日本の貢献: ダーウィン以来、動物と人間の連続性が議論されてきたが、社会や文化を非ヒト動物に適用する試みは、今西錦司を中心とする日本の霊長類学によって大きく前進した。個体に名前を付け長期観察する「個体識別法」は当初西洋で批判されたが、現在では動物行動学の標準手法となっている。この手法により、ニホンザルの母系社会や「末子優位」の法則、幸島のサルの「イモ洗い」に代表される文化行動などが発見された。
- 人類の根源的性質と進化の道筋: 人類を他の類人猿から区別する根源的特徴は、従来考えられていた大きな脳ではなく「直立二足歩行」である。約700万年前に始まったこの歩行様式は、熱帯雨林からサバンナへ進出した初期人類が広範囲の食物探索と運搬をエネルギー効率よく行うことを可能にした。脳の大脳化はその後、肉食導入や火の利用による消化効率の向上という「食物革命」を背景に、約200万年前から本格化した。
- 社会形成の二大要因—食と性: 霊長類の社会構造は「食」と「性」によって大きく規定される。食物の分布(葉食者 vs. 果実食者)は遊動域や群れの競合関係を決定する。類人猿の消極的な食物分配に対し、人は仲間と共食するために食物を運び積極的に分配する。この行動と、大脳化に伴う長期育児を共同で行う「共同保育」が、人に固有の「共感」能力の基盤となった。性皮腫脹の有無や睾丸の相対的サイズなどの性的特徴は、複雄群や単雄群といった社会構造と密接に関連する。
- 暴力の起源とコミュニケーションの進化: 人類が本性として暴力的だったとする「狩猟仮説」は誤りであり、人類は進化の大半を捕食者に怯える「被食者」として過ごしてきた。組織的な暴力(戦争)は、約1万年前の農耕開始以降、定住と所有の概念が生じてから顕在化した。葛藤解決の方法として、ニホンザルは厳格な順位制を用いるが、ゴリラやチンパンジー、そして人は互いの目を見つめ合う「対面コミュニケーション」によって関係を調整する。
- 共感社会の未来: 言語の登場は約7万年前と、脳の大脳化に比べて新しい。言語に先立ち音楽的コミュニケーションが集団の感情を同調させ、共感と協調性を高めた。言語は「認知的流動性」を生み象徴的思考を可能にしたが、現代の情報技術は身体性を伴わないコミュニケーションを増やしている。これにより、長い時間をかけて育まれてきた共感に基づく社会が、個人の利益を優先する「サル化」した社会へと変容する危機に瀕しており、身体的つながりを通じた社会資本の回復が現代の課題となっている。
1. 霊長類学のパラダイムシフト:社会と文化の再定義
ヒト固有とされてきた「社会」や「文化」の概念は、霊長類学、特に日本の研究者の貢献によって大きく拡張された。動物とヒトの社会を連続的に捉える視点は、人類の社会性の起源を探る上で不可欠な基盤となっている。
1.1. 動物社会学の黎明と日本の貢献
- ダーウィンの予言: チャールズ・ダーウィンは『人間の由来』で、初めて「社会」をヒト以外の動物に適用し、個体間関係が進化の舞台となることを示唆した。
- 学問の分断: 20世紀初頭の西洋では、社会進化論が植民地主義や優生思想に利用された反動で、社会や文化を自然科学の対象とすることが避けられ、人類学と動物行動学の間に隔たりが生じた。
- 今西錦司の方法論: 京都大学の今西錦司は以下の3点を重視する方法論を確立した。
- 種ごとの社会を比較する比較社会学の適用
- 個体識別法(個体に名前を付け追跡する)
- 長期継続観察による社会交渉の記録
- 世界標準への道: 個体に名前を付ける手法は当初「擬人主義」として批判されたが、ジェーン・グドールらのチンパンジー研究の成功もあり、その有効性が認められ、現在は動物行動学の標準手法となっている。
1.2. ニホンザル研究が明らかにした社会構造と文化
日本の霊長類学はニホンザルの長期研究から多くの発見をもたらした。
- 構造化された社会: 伊谷純一郎は、ニホンザルの群れが単なる個体の寄せ集めではなく、直線的な優劣順位や二重同心円の空間構造を持つ「社会」であることを示した。
- 母系社会のルール:
- 末子優位の法則: 姉妹間では母親の庇護により妹が姉より優位となり、この関係は成長後も維持される。
- 家系順位: メスの順位は母系によって決まり、生涯を通じて継承される。
- 文化の概念拡張と「プレカルチュア」: 今西は「文化」を遺伝に依らず伝わる行動様式と再定義し、ニホンザルの社会ルールをその一種(プレカルチュア)と考えた。
- 幸島のイモ洗い: 1954年に宮崎県幸島で観察された、若いメスザルが始めたサツマイモを海水で洗う行動が仲間や次世代に伝播した事例は、模倣によって学習される文化行動の初期段階の好例である。
1.3. 環境が社会を形成する:ニホンザルの比較研究
ニホンザルは亜熱帯から冷帯まで多様な環境に生息するため、環境要因が社会構造に与える影響の比較研究が可能である。特に屋久島(常緑樹林・高栄養)と金華山島(落葉樹林・低栄養)での比較は重要な知見をもたらした。
(表は保持)
この比較から、環境が群れ間関係を規定し、群れ間関係がオスの行動様式や群れの構造を決定する、というモデルが導かれた。屋久島では資源を巡る群れ間闘争が激しいため、防衛力となる強いオスを多く受け入れる傾向が生じ、結果として群れのオス割合が高くなる。
2. 人類進化の道筋:サバンナへの進出と身体の変化
霊長類の祖先は熱帯雨林で誕生し、樹上生活に適応する中で基本的な身体特徴を進化させた。しかし人類の祖先だけが森を出てサバンナへ進出し、そこで独自の進化の道を歩んだ。
2.1. 人類の根源的特徴:直立二足歩行
- 進化の舞台: 人類進化の約4分の3はアフリカの乾燥地帯で進行した。気候変動で熱帯雨林が縮小しサバンナが拡大する中、祖先は森の外へ進出した。
- 知性ではなく歩行: 20世紀半ばまでは根源的特徴は大きな脳と考えられていたが、化石では脳の大脳化(約200万年前〜)より前の約700万年前に直立二足歩行が既に成立していたことが示された。
- 直立二足歩行の利点: 高速移動には不向きだが、時速約4kmのゆっくりした速度で長距離を移動する際に四足歩行よりエネルギー効率が良い。これによりまばらに分布する食物を探し長距離を歩き、見つけた食物を安全なねぐらへ運ぶ生活が可能になった。
2.2. 大脳化とそれを可能にした食物革命
ヒトの大きな脳は進化上の大きなエネルギー負担であり、その発達は食生活の劇的な変化によって支えられた。
- 肉食の導入: 約250万年前にオルドワン式石器が登場し、動物の死骸から肉を切り取ることが可能になった。肉は葉の10〜20倍のカロリーを含み、脳増大に必要なエネルギーを供給した。
- 火と調理: 約100万年前頃から火の使用が始まり、調理によって消化効率が向上し利用可能な食物の幅が広がった。
- 「高価な臓器」仮説: ヒトは大きな脳を持ちながら基礎代謝が特別に高いわけではない。脳を大きくする代わりに消化効率の高い食物(肉や調理食)を摂り、結果として消化器系を小さくしたためだと考えられている。
3. 社会形成の二大要因:食と性
霊長類の多様な社会は主に「食」と「性」によって形成される。人類の特異性も食と性の進化に深く根ざしている。
3.1. 食が社会を形作る
食物の性質と分布は霊長類の行動と社会関係に直接影響する。
- 葉食者と果実食者の対比:
- 葉食者(例:ゴリラ): 葉は豊富に存在するため遊動域は狭く群れ間競合は少ない。消化に時間がかかるため活動リズムは採食と休息に分かれる。
- 果実食者(例:チンパンジー): 果実はパッチ状に分布するため遊動域は広く、群れ間資源競合が激しい。
- 食物分配の進化:
- 類人猿の消極的分配: 下位個体がねだった場合に限り上位個体が食物を分ける「消極的分配」が見られる。
- ヒトの積極的分配: ヒトは食物を運んで仲間と共食し、積極的に分配する。この行動が共感と信頼関係を育んだ。
3.2. 性が社会を形作る
性のあり方は社会構造と密接に関連する。
- 性皮腫脹と社会: 排卵期に尻が腫脹する種は多くのオスを惹きつけ、複雄複雌群を形成する傾向がある。
- 睾丸サイズと社会: オスの睾丸が相対的に大きい種(例:チンパンジー)は精子競争が激しい複雄群を形成し、睾丸が小さい種(例:ゴリラ)は単雄群を形成する傾向がある。
- ヒトの特殊性: ヒトは性皮腫脹を示さないが、女性の恒常的に大きい乳房や男性の大きな陰茎など類人猿と異なる性的特徴を持つ。これらは一夫一妻制と必ずしも整合せず、祖先が経験した複雑な社会史を反映している可能性がある。ヒトは家族が複数集まって地域集団を形成する「重層社会」を持つ点でも独特である。
4. 暴力の起源と葛藤解決の進化
人間の暴力性に関する通説は霊長類学の知見によって再検討されている。暴力は人類の本性ではなく、社会の複雑化に伴って特定文脈で顕在化したものである。
4.1. 暴力に関する誤解:「狩猟仮説」の否定
- 人類は被食者だった: 人類が優れた狩猟者として進化したとする「狩猟仮説」は、考古学的証拠と矛盾する。狩猟具の登場(約50万年前)や集団闘争の確実な証拠(約1万年前)は人類史700万年のごく最近の出来事であり、進化の大半で人類は肉食獣に捕食されうる弱い存在だった。
- 暴力の二面性:
- 他種への攻撃(狩猟): 生存のための攻撃行動。
- 同種への攻撃: 資源争奪を調整する社会的行動。
4.2. 葛藤解決の様式
| 種 | 葛藤解決の様式 | 特徴 |
| ニホンザル | 順位制に基づく交渉 | ・厳格な直線的順位が存在。 ・上位個体が下位個体の目を見ることは「威嚇」を意味する。 ・第三者は、自身の順位を守るために介入する。 |
| 類人猿・ヒト | 対面コミュニケーション | ・顔を寄せ合い、互いの目を見つめ合うことで「仲直り」や挨拶を行う。 ・第三者が仲裁のために介入することが多い。 ・ヒトは特に白目が大きく、視線による意図伝達能力が高い。 |
- ニホンザル: 厳格な直線的順位制があり、上位個体が下位個体の目を見ることは威嚇を意味する。第三者は自身の順位を守るために介入する。
- 類人猿・ヒト: 顔を寄せ目を見つめ合うことで仲直りや挨拶を行う対面コミュニケーションを用いる。第三者が仲裁に入ることが多い。ヒトは白目が大きく視線による意図伝達能力が高い。
4.3. 子殺しの社会生物学
「子殺し」はオスの繁殖戦略として説明されることがある。
- 機能: 群れを乗っ取った新しいオスが前のオスの乳飲み子を殺すことでメスの授乳を終わらせ、発情を早めて自分の子を残す。
- 発生条件: オスがメスより大きく授乳期間が長い複雄複雌群などで起きやすい。
- 対抗戦略と社会への影響: メスは偽の発情などで対抗する。マウンテンゴリラでは子殺しの脅威が高い地域ほど複数オスによる防衛的複雄群が形成されやすいなど、子殺しは社会構造に影響を与える。
5. 共感社会の誕生:ヒトの特殊な生活史とコミュニケーション
ヒトの社会性の核心は「共感」能力にある。この能力は他の霊長類と一線を画すヒト固有の生活史と、それに伴うコミュニケーションの進化によって育まれた。
5.1. ヒトの特殊な生活史と家族の形成
- 霊長類の生活史: 霊長類は哺乳類の中でも成長が遅く長寿である。
- ヒト固有の生活史段階: 類人猿共通の「乳児期」「子ども期」「成人期」「老年期」に加え、ヒトは以下の段階を持つ。
- 幼年期:離乳後だが大人と同じものを食べられない時期
- 青年期:性的に成熟しているがまだ繁殖を開始しない時期
- 進化の背景: サバンナ進出で乳児死亡率が高まったため出産間隔を短める「多産化」が進み、離乳が早まり幼年期が生じた。脳にエネルギーを優先的に使うため身体成長が遅れ、青年期の思春期スパートが生じた。
- 家族と共同保育の誕生: 幼年期や青年期の子を育てるには母だけでなく父や他者の協力が不可欠となり、この「共同保育」が家族という単位と他者を思いやる「共感性」を生む土壌となった。閉経後も長く生きる「老年期」(おばあちゃん仮説)も共同保育を支える重要な要素であった。
5.2. コミュニケーション革命:音楽から言語へ
ヒトの高い共感性は独自のコミュニケーション手段によって支えられ増幅された。
- 音楽の先行: 言語よりずっと以前に音楽的コミュニケーションが発達したと考えられる。テナガザルのデュエットやゴリラのハミングのように、音楽は感情を直接伝え身体を共鳴させ集団の同調性を高める効果がある。
- 共同育児と音楽: 泣きやすい人間の赤ん坊をあやすために世界共通の音楽的特徴を持つ声(マザリーズ)が使われ、子守唄のやり取りが人間の音楽能力を高めた可能性がある。
- 言語の登場とその影響: 言語の確実な証拠は約7万年前と比較的新しく、脳の大脳化の結果として獲得された。言語は独立していた認知モジュール(道具的知能、技術的知能、社会的知能など)を結びつけ「認知的流動性」を生み、比喩や抽象思考を可能にし、約4万年前の「創造的爆発(社会文化的大変化)」につながった。
6. 人類社会の変容と未来への展望
人類が築いた共感社会は、農耕牧畜の開始以降、特に現代の情報社会において大きな変容を受けている。
6.1. 農耕牧畜がもたらした変化
- 所有と定住: 約1万2千年前に始まった農耕牧畜は定住を促し、土地や食料を管理・蓄積する「所有」の概念を生んだ。これは共有と平等な分配を原則とする狩猟採集社会からの大きな転換であった。
- 組織的暴力の起源: 土地への執着と人口増加は縄張り意識を強め、集団間の争いを頻発させた。共感能力は内部結束を強める一方で、外部に対する攻撃性を増幅し、組織的な暴力(戦争)へとつながった。
6.2. 現代社会の課題:「サル化」する人間社会
未来への展望: 家族や共同体といった、かつて安心を保障していた社会資本が揺らぐ中で、人々は無意識に身体的な同調を求めている(スポーツ観戦やコンサートなど)。情報技術の利点を活かしつつ、衣食住といった暮らしの基本を再び「わかちあう」工夫により、新しい形の家族や共同体を再構築し、共感に基づいた信頼関係を取り戻すことが未来の課題となるだろう。
コミュニケーションの変容: インターネットやスマートフォンは時間と場所を超えた効率的な情報伝達を可能にしたが、同時に身体性を伴う対面コミュニケーションの機会を減少させた。
共感社会の危機: 身体的つながりで育まれてきた共感に基づく社会が、個人の利益や効率を優先する社会へ変わりつつある。この傾向は優劣のルールに基づいて個体が利己的に振る舞うサルの社会に似ており、「サル化」と形容される。
- 霊長類学の歩んできた道
- 第一節 夜明け前
- 1 ダーウィンが開いた動物社会学の道
- 2 ヒトは類人猿
- 3 動物にも「社会」はあるのか
- 4 ヒト社会の解明に立ちはだかる壁
- 5 分断された社会進化の科学
- 6 動物の個性:エンターテイメントと科学の乖離
- 7 誤解されたゴリラ
- 8 ドラミングの本当の意味
- 9 霊長類学がヒト祖先の社会を紐解く
- 第二節 日本霊長類学のはじまり
- 10 動物社会学と動物への「名付け」
- 11 ニホンザルとの出会い
- 12 今西錦司の方法論
- 13 ニホンザルの社会がみえてきた
- 14 世界標準になった今西の観察法
- 第三節 サルに文化はあるか
- 15 日本霊長類学が掲げた目標
- 16 ニホンザルにみる「末子優位」の法則
- 17 ニホンザルのメスの家系順位
- 18 今西による「文化」概念の拡張
- 19 幸島のサルのイモ洗い
- 20 群れに伝わったイモ洗い
- 21 サルのイモ洗いは「文化」か?
- 第四節 ニホンザルから類人猿へ
- 22 ヒトの家族≠動物の群れ?
- 23 家族の前提条件
- 24 ゴリラに引き寄せられた東西の研究者
- 25 シャラーによるゴリラの「人付け」
- 26 ダイアン・フォッシー
- 27 フォッシーの戦いと死
- 28 伊谷とグドールの出会い
- 29 グドールに対する批判
- 第一節 夜明け前
- ニホンザルの社会とは
- 第一節 霊長類の社会進化モデル
- 30 伊谷の霊長類社会進化モデル
- 31 人間平等起源論
- 32 ヴァン・シャイクらの社会生態学モデル
- 33 社会進化モデルの課題
- 第二節 北限のサルの研究史
- 34 ニホンザルの起源
- 35 ニホンザルの基礎知識
- 36 餌付けによる影響
- 37 屋久島と金華山島、環境の違い
- 38 ニホンザルの行動の比較
- 39 ニホンザルの社会構造の比較
- 40 環境要因以外に、何が社会を決める?
- 第三節 ニホンザル社会の共通点と地域差
- 41 群れ間関係の地域差
- 42 屋久島のオスの戦略
- 43 単独オスの群れ移入の仕方の地域差
- 44 群れに入ってはまた出ていくオスたち
- 45 環境が群れ間関係をつくり、群れ間関係がオスの行動を決める
- 46 群れの分裂
- 47 群れの周りに集うオス
- 48 交尾期の親密な雌雄が引き起こす群れの分裂
- 49 交尾期の群れ分裂が群れサイズを決める
- 50 ニホンザル社会の共通点と多様性
- 第一節 霊長類の社会進化モデル
- 霊長類進化の舞台
- 第一節 熱帯雨林:霊長類が進化した場所
- 51 熱帯雨林の分布と気候
- 52 今の霊長類、昔の霊長類
- 53 人類誕生の地は?
- 第二節 アフリカ熱帯林における霊長類の適応
- 54 樹上生活での移動方法
- 55 移動方法と手足の形
- 56 食物と体の大きさ
- 57 食物と消化器官
- 58 鳥の食卓を奪う
- 59 昼の世界がサルを変えた
- 第三節 森を出た人類
- 60 気候変動で広がった霊長類の分布
- 61 サバンナへの進出が新たな種を生んだ
- 62 三百種の霊長類
- 63 四属七種の大型類人猿
- 64 二種のゴリラ
- 65 チンパンジーとボノボ
- 66 サバンナに進出した初期人類
- 67 人類はアフリカで進化した
- 68 サバンナでの暮らしから「出アフリカ」へ
- 第四節 人類祖先の道程
- 69 サバンナに出た人類祖先
- 70 高い知性こそ人類の根源的性質?
- 71 否、直立二足歩行こそ人類の根源的性質
- 72 直立二足歩行がもたらしたもの
- 73 直立二足歩行の利点
- 第五節 ゴリラとチンパンジーの共存
- 74 二種の類人猿が暮らす中部アフリカ熱帯林
- 75 ゴリラとチンパンジーの生態的分化
- 76 食物がゴリラとチンパンジーの社会を分けた?
- 77 驚くほど似通っていた低地のゴリラとチンパンジー
- 第六節 山極による同所的類人猿の研究
- 78 主要でない食物に現れた両種の違い
- 79 ゴリラとチンパンジー、群れの遊動の違い
- 80 動き続けるゴリラ、同じところに留まるチンパンジー
- 81 ゴリラとチンパンジー、それぞれの採食戦略
- 82 食性の違いが類人猿の分布を決める
- 83 初期人類の採食戦略は?
- 第一節 熱帯雨林:霊長類が進化した場所
- 食と性が社会性をつくる
- 第一節 食物が霊長類社会に与える影響
- 84 葉食者と果実食者:遊動域の違い
- 85 葉食者と果実食者:活動リズムの違い
- 86 食物と天敵がメスの社会性を決め、メスの社会性がオスの社会性を決める
- 第二節 食物分配と社会性
- 87 霊長類の消極的食物分配
- 88 食物分配をするサル、しないサル
- 89 ゴリラのオトナどうしは食物を分配しない?
- 90 ついに発見したニシローランドゴリラの食物分配
- 第三節 人類進化と食物分配
- 91 類人猿とヒトの食物分配の違い
- 92 厳しい環境が積極的食物分配というコミュニケーションを進化させた
- 93 肉食の導入
- 94 火の使用と脳の増大
- 95 脳の増大とヒトの集団
- 96 脳の増大とヒトの社会性
- 第四節 霊長類の社会性をかたちづくる「性」
- 97 霊長類の性皮腫脹
- 98 霊長類の月経周期
- 99 性行動を引き起こすシグナルは?
- 100 性皮腫脹でオスを「だます」
- 101 オスは的外れな交尾を挑み、メスはそれを拒む
- 102 性と社会との関係
- 103 ヒトの性的特徴
- 104 ヒトの特殊な性的特徴は、祖先的社会の反映か?
- 第五節 ヒトの性と社会進化
- 105 類人猿の社会
- 106 ヒトの特徴は類人猿の「モザイク」
- 107 類人猿の中でヒトだけが重層社会をもつ
- 108 人類祖先の社会構造は?
- 第一節 食物が霊長類社会に与える影響
- 暴力と社会
- 第一節 人類は狩猟者として進化した?
- 1 暴力の霊長類的起源
- 2 狩猟仮説
- 3 狩猟仮説と「二〇〇一年宇宙の旅」
- 4 戦争は人類の本質ではない
- 5 人類は狩猟者ではなく被食者だった
- 第二節 攻撃性と社会的知性
- 6 他種に対する攻撃、同種に対する攻撃
- 7 どのように資源をめぐる競合を解決するか?
- 8 ニホンザルの直線的順位
- 9 ニホンザルの三者間攻撃交渉
- 10 直線的順位に基づいた社会的知性
- 11 厳しい順位関係と相手の目を見る「威嚇」
- 第三節 対面コミュニケーションの意味
- 12 第三者による攻撃交渉への介入
- 13 類人猿は目を見つめあって「仲直り」する
- 14 対面コミュニケーションはヒト科共通
- 15 ヒトの「過剰な」対面コミュニケーション
- 16 ヒトの横長な眼と大きな白目
- 第四節 霊長類の子殺し
- 17 子殺しの発見
- 18 メスは「殺し屋」のリーダーオスと交尾をする
- 19 子殺しはオスの繁殖戦略
- 20 子殺しが起きる種、起きない種
- 21 子殺しが起きる条件
- 22 偽の発情で子殺しを防ぐボノボのメス
- 23 子殺しを防ぐ要因と人類の進化
- 第五節 ゴリラの子殺し行動と社会の多様性
- 24 子殺しが起きる頻度は地域によって異なる
- 25 オス間関係の地域差
- 26 マウンテンゴリラで複雄群ができる理由
- 27 子殺し行動の共通点:誰が殺すか、子を殺された母の行動
- 28 子殺しを避けるため、単独で移籍するヴィルンガの母ゴリラ
- 29 子殺し行動が複雄群を増やすメカニズム
- 第一節 人類は狩猟者として進化した?
- 生活史戦略の進化
- 第一節 霊長類の生活史と分散パターン
- 30 霊長類はゆっくりした生活史を持つ哺乳類
- 31 環境と社会が生活史に影響する
- 32 メス居住種とメス分散種
- 33 メス分散種は繁殖のスピードが遅くなる
- 第二節 ヒトと類人猿の生活史
- 34 大型類人猿の生活史
- 35 ヒトの特殊な生活史
- 36 ヒトに固有な「幼年期」と「青年期」
- 37 ヒトの特殊な生活史はなぜ進化した?
- 第三節 サバンナへの進出から家族の形成へ
- 38 サバンナ進出が早い離乳と多産をもたらした
- 39 早期離乳が赤ん坊の「離乳食」を必要とした
- 40 大脳化
- 41 思春期スパートと「青年期」の進化
- 42 家族と共感性の誕生
- 43 難産と長い老年期
- 第四節 大脳化と人類の行動進化
- 44 なぜ大脳化が起きた?
- 45 脳はエネルギーを大量に消費する
- 46 人類の行動的進化① :二足歩行に伴う性的役割分担
- 47 人類の行動的進化② :動物食の増加
- 48 人類の行動的進化③ :火の使用と調理
- 49 人類の行動的進化④ :農業
- 50 『高価な臓器』仮説
- 51 脳を大きくする代わりに胃腸を小さくした人類
- 52 肉食と調理が可能にした胃腸の縮小
- 第一節 霊長類の生活史と分散パターン
- 心の理論とコミュニケーション革命
- 第一節 サルのコミュニケーション
- 53 サルの警戒音
- 54 ミラーニューロンの発見
- 55 ニホンザルのイモ洗い行動
- 56 サルは模倣が苦手
- 57 類人猿の模倣能力
- 58 アイデンティフィケーション
- 第二節 仲間を思いやる能力
- 59 サルの同情能力
- 60 ビンティの美談
- 61 類人猿の他者をいたわる行動
- 第三節 心の理論と利他行動
- 62 自己の鏡像理解
- 63 チンパンジーの他者理解
- 64 仲間をだます行動
- 65 動物の教示行動
- 66 互酬的な行動
- 第四節 共同保育と共感能力
- 67 子どもに食物を与えることから食物分配は広まった
- 68 子どもに手がかかる種に食物分配が現れた
- 69 危険な環境が人間に食物分配を促進させた
- 70 マーモセット類の父性行動と思いやり行動
- 71 ゴリラの父性行動とインセスト回避
- 72 人間の父性の起源
- 第五節 音楽的能力の進化
- 73 テナガザルのテリトリーソング
- 74 霊長類の音声レパートリー
- 75 ゲラダヒヒの会話
- 76 類人猿の音声
- 77 直立二足歩行と音楽の能力
- 78 踊る身体の獲得
- 79 共同育児と音楽
- 80 絶対音感で生まれる赤ん坊
- 第六節 音楽から言語へ
- 81 言葉は脳を大きくした原因ではなく、結果である
- 82 社会集団のマジック・ナンバー
- 83 集団規模の違いによるコミュニケーション
- 84 Fox P2遺伝子と言語能力
- 85 言語の起源をめぐる2つの仮説
- 86 奉仕する心と家族
- 第一節 サルのコミュニケーション
- 家族の変容とヒト社会の未来
- 第一節 人間家族と創造的爆発
- 87 言語と認知的流動性
- 88 創造的爆発
- 89 サピエンスとネアンデルタール
- 第二節 採集狩猟から農耕牧畜へ
- 90 狩猟動物の大量絶滅
- 91 家畜になった動物たち
- 92 食糧生産の始まり
- 93 家畜化と農業の振興
- 第三節 社会の拡大と暴力の起源
- 94 分かち合いと所有
- 95 定住と縄張り意識
- 96 暴力の拡大
- 97 暴力を生み出す心
- 98 首長制社会の登場
- 第四節 現代社会とコミュニケーションの変容
- 99 対面コミュニケーションと身体のつながり
- 100 言語による意識の変容
- 101 文字の登場と情報機器の改良
- 102 対面コミュニケーションの減少と効率的な暮らし
- 第五節 家族の未来と超スマート社会
- 103 裸にされる個人
- 104 サル化する現代社会
- 105 サル化する現代社会 その二
- 106 自由主義経済とグローバル化
- 107 共感力の発揮と社会資本の回復
- 108 情報・通信機器の賢い利用とネットワーク社会
- 109 均質な社会のコミュニケーション
- 110 未来の家族
- 第一節 人間家族と創造的爆発
- おわりに
Mのコメント(言語空間・位置付け・批判的思考)
ここでは、対象となる本の言語空間がどのようなものか(記述の内容と方法は何か)、それは総体的な世界(言語世界)の中にどのように位置付けられるのか(意味・価値を持つのか)を、批判的思考をツールにして検討していきたいと思います。ただサイト全体の多くの本の紹介の整理でアタフタしているので、個々の本のMのコメントは「追って」にします。