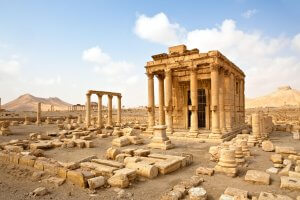暴力と紛争の“集団心理”_への道標
書誌_暴力と紛争の“集団心理” いがみ合う世界への社会心理学からのアプローチ:縄田健悟

短い紹介と大目次
短い紹介
本書は、暴力と紛争における集団心理のメカニズムを、社会心理学の視点から体系的に解説したものである。人間が厳しい環境を生き延びるための協力的戦略として集団を形成してきた歴史的背景から始まり、集団に所属することで生じる「集団モード」という心理状態が、暴力行為にどのように結びつくのかを深く掘り下げている。特に、多くの人を救うためでも「自分の手で」危害を加えることに強い拒否感が生じるというグリーンの研究や、社会的報酬(賞賛や名誉)の獲得が暴力への動機付けとなる進化的な適応価が示唆される点、さらには集団からの拒否回避が暴行やジェノサイドへの加担を促す側面など、多角的な研究結果が提示されている。最終的に、文明化の潮流に伴う反暴力的規範の広がりが、将来的な暴力と紛争の低減に寄与すると展望している。
大目次
- はじめに
- 序章 暴力と紛争の〝集団心理〟 社会心理学の視点から
- 第Ⅰ部 内集団過程と集団モード
- 第1章 集団への愛は暴力を生み出すか?
- 第2章 集団への埋没と暴力 没個性化、暴動
- 第3章 「空気」が生み出す集団暴力
- 第4章 賞賛を獲得するための暴力 英雄型集団暴力
- 第5章 拒否を回避するための暴力 村八分回避型集団暴力
- 第Ⅱ部 外集団への認知と集団間相互作用過程
- 第6章 人間はヨソ者をどう見ているのか? 偏見の科学
- 第7章 「敵」だと認定されるヨソ者 脅威と非人間化
- 第8章 報復が引き起こす紛争の激化
- 第Ⅲ部 暴力と紛争の解消を目指して
- 第9章 どうやって関わり合えばよいのか? 暴力と紛争の解消を目指して
- あとがきに代えて
- 図表の出典
- 注・文献
- 人名索引
- 事項索引
一口コメント
要約と詳細目次
暴力と紛争の集団心理に関するブリーフィング
要旨
本書「暴力と紛争の“集団心理”」は、人間が本質的に暴力を嫌うにもかかわらず、なぜ戦争、紛争、いじめといった集団的暴力が生じるのかを、社会心理学の知見を統合して体系的に説明しようとする。核心は、集団が「暴力誘発装置」として機能しうるという視点である。
本書はこの現象を解明する鍵として独自の概念「集団モード」を提唱する。これは、特定の状況で心理的スイッチが入り、個人の心理状態が集団中心の状態に移行する現象を指す。「集団モード」は主に二つに分類される。
- コミット型集団モード:個人が自己を集団と同一視し、集団のために滅私奉公的に行動する心理状態。愛国心に基づく自己犠牲的攻撃(アイデンティティ融合)、匿名性による規範への同調(没個性化)、権威への服従(ミルグラム実験)などがこのモードで説明される。このモード自体は本質的に悪ではないが、集団が暴力的・排他的な規範を持つ場合、暴力を増幅させる。
- 生存戦略型集団モード:集団内での自己の立ち位置や評判を維持・向上させるために戦略的に行動する心理状態。二つの側面がある。
- 英雄型集団暴力:仲間からの賞賛や高評価を得るために英雄的に振る舞い、積極的に攻撃する。「名誉の文化」や非行集団で顕著に見られる。
- 村八分回避型集団暴力:集団からの拒否や排斥を恐れて、本心では望んでいなくても攻撃行動に加担する。
本書はこれらの理論枠組みに基づき、外集団への歪んだ認知(偏見、脅威、非人間化)や報復の連鎖といった紛争激化のプロセスを分析し、紛争解決へのアプローチを提示する。結論として、非日常に見える集団暴力は日常的な集団心理の延長線上にあり、「集団モード」のメカニズム理解が暴力と紛争抑制の鍵であると論じる。
1. 序論:暴力と紛争の「集団心理」へのアプローチ
本書は社会心理学の観点から、戦争、テロ、いじめといった集団的暴力と紛争の根底にある「集団心理」を体系的に解明することを目的とする。著者・縄田健悟氏は、自身が非暴力的であるゆえに人々が集団のために暴力を振るう現象に疑問を抱いたことが研究の出発点であると述べる。
1.1. 人間の本性と集団
人間は厳しい環境を生き抜くために集団で協力する戦略を採用してきた。集団生活は協力やコミュニケーション能力を発展させ、人類の繁栄に寄与したが、一方で「影」の側面もある。戦争、虐殺、差別、いじめといった暴力は多く集団という文脈で発生する。本書は、集団が持つ「暴力誘発装置」としての機能に注目する。
1.2. 根本的な問い:なぜ暴力嫌いの人間が暴力を振るうのか
研究によれば、人間は自ら暴力を振るうことを強く嫌悪する。これは「他者に危害を加えてはならない」という道徳的価値判断(道徳基盤理論の「ケア/危害回避」)に根ざしている。軍事心理学者グロスマンは、戦場でさえ兵士のうち発砲するのは約15%に留まると指摘する。
この暴力への根源的忌避にもかかわらず現実世界が暴力に満ちている理由を、本書は「集団」に求める。
1.3. 分析の枠組み:「集団モード」
本書の中心概念は「集団モード」である。特定の状況的手がかりにより心理的スイッチが入り、個人の心理状態が集団に関するモードへ切り替わる状態を指す。集団モードは大きく二つに分類される。
| 集団モードのタイプ | 説明 | 特徴 | 関連する心理概念 |
|---|---|---|---|
| ⓐ コミット型 | 集団の一員として自己を捉え、集団中心に思考し、自己犠牲も辞さないモード | 「我々 対 奴ら」の視点が強まり、自集団中心主義に陥りやすい | 内集団同一視、社会的アイデンティティ、アイデンティティ融合、没個性化、服従 |
| ⓑ 生存戦略型 | 集団内での評判や立ち位置を調整し、生き残るために戦略的に振る舞うモード | 他者からの評価への関心が高まる | 評判、自己呈示、印象管理、賞賛獲得、拒否回避、多元的無知 |
これらのモードは相互に排他的でなく、同時に存在しうる。本書はこれらが愛国心、匿名性、権威、評判などと結びつき、いかに集団暴力を引き起こすかを分析する。
2. 第Ⅰ部 内集団過程と集団モード
第I部では、コミット型と生存戦略型の二つの集団モードが、内集団のプロセスにおいてどのように暴力を誘発するかを詳述する。
2.1. コミット型集団モードと暴力
a) 集団への愛は暴力を生むか?(第1章)
「内集団への愛(愛国心など)が強いほど、外集団への暴力は強まるか?」という問いに対し、答えは「単純にはNO、しかし条件付きでYES」である。集団アイデンティティ(内集団同一視)自体は直接に外集団への攻撃性を高めないが、以下の二つの条件下では暴力に結びつく。
- 条件1:集団間が紛争・競争状況にあるとき
- 集団アイデンティティが強い人は「私=私の集団」と認識するため、集団への攻撃を自己への攻撃と捉え、怒りを感じ報復を支持しやすくなる(集団間感情理論)。9.11後のアメリカ人の報復支持が例として挙げられる。
- 極端な例がアイデンティティ融合で、自己と集団が一体化し、集団のために命を賭して戦う自己犠牲的攻撃(例:特攻隊、テロリスト)につながる。
- 条件2:集団アイデンティティの「優越性・支配性」の側面が強調されるとき
- 集団への愛着(パトリオティズム)は攻撃性と関連が低いが、自集団を他集団より優れていると見なし支配を求める国家主義(ナショナリズム)は外集団への攻撃性と強く関連する。
- 集団の優越性が脅かされることに過敏に反応する集合的ナルシシズムも外集団への攻撃性を引き起こす。彼らは特権意識から些細な侮辱にも過剰に反撃する。
b) 集団への埋没と暴力(第2章)
群衆の暴徒化は、集団への埋没と匿名性による「没個性化」で説明される。
- 古典的理論(自己意識の低下):匿名性が高まると自己への注意が低下し、道徳的抑制が失われ反社会的行動が解放される(ジンバルドの実験など)。化粧や覆面が戦争の残虐性を高めることを示す研究もある。
- 現代的解釈(SIDEモデル):没個性化は単なる自己喪失ではなく、「個人的アイデンティティ」から「社会的アイデンティティ」への移行である(没個性化の社会的アイデンティティ・モデル:SIDEモデル)。匿名性はコミット型集団モードのスイッチを入れ、その場の集団規範への同調を促す。
- 集団規範が暴力的であれば暴力は促進され(例:KKKの服装での実験)、規範が向社会的であれば暴力は抑制される(例:ナース服での実験)。
- セントポール暴動の分析では、暴徒は無秩序に破壊活動を行ったのではなく、「セントポール住民 対 警察」という集団間紛争の構図のもと、警察を選択的に攻撃しており、集団規範に従った行動であった。インターネット上の炎上も同様のメカニズムで説明される。
c) 「空気」が生み出す集団暴力(第3章)
集団の「空気」(集団規範)や権威への服従は、暴力の強力な誘因となる。
- 権威への服従(ミルグラム実験):権威者の指示に従い他者に致死レベルの電気ショックを与えうることを示した。65%の参加者が最後まで服従したこの結果は国や時代を超えて再現されている。
- 近年の再解釈では、これは盲目的服従ではなく、参加者が科学の進歩という大義にコミットし、実験者と自らを同一視する「従事的フォロワーシップ」の結果だとされる。暴力的行為を指示する「アイデンティティ・リーダーシップ」のもと、参加者のコミット型集団モードがオンになったと理解される。
- 役割への同調(スタンフォード監獄実験):看守役と囚人役という役割を与えただけで看守が暴力的になり囚人が無気力になったとされるが、その再現性は疑問視される。BBCによる追試は再現せず、スタンフォード実験でも実験者が看守に「タフになる」よう促していたことが判明した。これもミルグラムと同様、実験者側への集団モードをオンにする「アイデンティティ・リーダーシップ」が暴力発生に寄与したと解釈される。
- アブグレイブ刑務所での虐待や学校でのいじめも「腐ったリンゴ」ではなく「腐った樽」、すなわち暴力を許容・推奨する集団規範が問題であると指摘される。
2.2. 生存戦略型集団モードと暴力
生存戦略型は集団内の評判や立ち位置を気にすることで、以下の二つの形で暴力を誘発する。
a) 賞賛獲得のための英雄型集団暴力(第4章)
攻撃すれば仲間から賞賛され英雄視されるという期待から行われる暴力。
- 暴力の賞賛:戦争の英雄、部族の戦士、一部の共同体内でのテロリストなど、特定の文脈で攻撃者は賞賛されてきた。
- 賞賛と攻撃の連関:著者の実験では、「報復すれば仲間から褒められる」と期待する人ほど外集団への代理報復(罰金)を強く行うことが示された。
- 名誉の文化:特に「男はタフであるべき」という価値観が根付く「名誉の文化」(例:アメリカ南部)では侮辱に暴力で応じることが男らしさの証とされ、賞賛される。こうした文化は戦士を称揚し、集団間紛争の頻度を高める傾向がある。非行集団でも暴力が「格好いい」と賞賛される局所的文化が存在する。
b) 拒否回避のための村八分回避型集団暴力(第5章)
集団から拒否されることを恐れ、不本意ながら暴力に加担する。
- 非協力者への罰:戦争で非協力的な人物が「非国民」として迫害されるように、集団の協力行動(この文脈では集団暴力)に参加しない者は罰せられることがある。
- 拒否回避による暴力:
- 本心ではない差別の表明:著者の研究では、中国人が個人の考えよりも「中国社会全体が日本を嫌っている」という認識(空気)に影響され、人前で本心以上に反日的態度を表明する傾向があった。これは「非国民」と思われることを避けるためである。
- 空気の読み間違い(多元的無知):実際には多くの人が反対しているのに「自分以外は皆賛成」と誤認し、その誤った認識に同調することで、誰も望んでいない差別や暴力が集団全体で行われることがある。
- 内集団ひいき:仲間から「非協力者」と見なされないために内集団を不公平に優遇し、結果として外集団への差別や攻撃に繋がる。
- 事例:集団リンチの加害者供述には「やめようと言えなかった」「仲間外れにされたくなかった」という動機が見られる。ルワンダのジェノサイドや名誉殺人でも、加担しないと自分が殺されるという恐怖からやむなく殺戮に参加した事例が報告されている。
3. 第Ⅱ部 外集団への認知と集団間相互作用
第II部では、内集団が外集団をどのように歪んで認識し、その相互作用が紛争をどのように激化させるかを探る。
3.1. ヨソ者はどう見えるか? ― 偏見と認知バイアス(第6章)
集団モードが作動すると、外集団(ヨソ者)を歪んだ色眼鏡で見るようになる。
- 社会的カテゴリー化:「我々(内集団)」と「奴ら(外集団)」の間に心理的線引きを行うことで、内集団内の類似性(同化)と集団間の差異(対比)が強調される。
- ステレオタイプと偏見:この線引きに基づき外集団に「十把一絡げ」の否定的イメージ(ステレオタイプ)が適用され偏見が生じる。
- 偏見の維持メカニズム:
- 確証バイアス:ステレオタイプに合う情報に注目し、反する情報を無視して偏見を強化する。
- サブタイプ化:ステレオタイプに反する事例を「例外」として処理し、元のステレオタイプを維持する。
- 自集団中心的な認知バイアス:
- 究極的帰属エラー:内集団の悪行は状況のせいにし、外集団の悪行は本性のせいにする。
- 反発的低評価:敵対する外集団からの提案は内容にかかわらず低く評価する。
- 敵・味方分断思考:世の中を即座に「敵」と「味方」に分ける傾向が強いほど陰謀論を信じやすく、外国への脅威を感じやすい。
3.2. 「敵」としてのヨソ者 ― 脅威と非人間化(第7章)
紛争を特に悪化させる外集団認知として「脅威」と「非人間化」がある。
- 脅威:
- 外集団=怖い:潜在意識や扁桃体の賦活など、外集団が脅威と結びつく証拠が示されている。
- 脅威の二側面:経済や安全を脅かす「現実的脅威」と、価値観や文化を脅かす「象徴的脅威」の両方が外集団への否定的態度を強める。
- 防衛的先制攻撃:脅威を感じると「やられる前にやる」という論理で先制攻撃が正当化されやすくなる。
- 狙撃手バイアス:警察官が武器を持っていない人を武器ありと誤認して射殺しやすい現象。外見から脅威を自動的に感知してしまうことが原因である。
- 非人間化:
- 他者を人間以下と見なす:外集団を「ゴキブリ」「ウジ虫」「サル」など動物や物体と同一視する現象。
- 暴力の促進:非人間化は相手への共感や道徳的抑制を取り払い、攻撃を「害虫駆除」のように正当化してジェノサイドなど残虐行為を可能にする。
- 非人間化の形態:二次感情(後悔、希望など)を持たないと見る「人間性希薄化」や、「進化が遅れた未開な存在」と見なす露骨な非人間化など様々な形がある。
3.3. 報復の連鎖 ― 紛争の激化(第8章)
紛争拡大の主要因の一つが「報復」であり、特に集団間では「集団間代理報復」という形をとる。
- 集団間代理報復:ある集団のメンバーが危害を受けた際、被害者本人ではない同集団の別のメンバーが、加害者本人ではない加害者集団の別のメンバーに仕返しをすること。
- メカニズム:
- コミット型モード(社会的カテゴリー化)
- 内集団同一視:仲間への危害を「我々」への危害と捉え、自分のことのように怒る。
- 外集団実体性知覚:加害者個人ではなく「奴ら」という集団全体を一体と見なし、その集団の誰に報復してもよいと考える。
- 生存戦略型モード(英雄になるための報復)
- 仲間がやられたとき報復することは内集団への協力と見なされ賞賛される。著者の実験では、仲間に見られている(観衆効果)状況や協力期待があると代理報復が強まることが示された。
この代理報復は無関係な人々を次々巻き込み、報復の連鎖を生み紛争を雪だるま式に拡大させる。
4. 第Ⅲ部 暴力と紛争の解消に向けて(第9章)
最終章では、これまでの心理メカニズムに基づき、紛争を解消・低減するためのアプローチを議論する。目次によればアプローチは二つに大別される。
- 集団間アプローチ:敵対する集団間の関係を改善する。
- 集団間接触:異なる集団のメンバーが直接会う機会を設ける。
- 視点取得と共感:相手の立場に立って考える。
- 共通目標と上位集団アイデンティティ:協力して達成すべき共通目標を設定し、「我々」の範囲をより大きな集団(例:「日本人」と「中国人」ではなく「地球市民」)へと再カテゴリー化する。
- 集団内アプローチ:各集団の内部を変革する。
多様性(ダイバーシティ)と包摂性(インクルージョン):異質な他者を排斥せず集団内に包摂することで、排斥から生まれる暴力を防ぐ。
反暴力的な規範・風土の変革:集団や社会全体で暴力を許容・賞賛しない規範を醸成する。第4章で述べたように、英雄型集団暴力は暴力が賞賛される文化で発生するため、この文化を変えることが根本的解決となる。
- はじめに
- 序 章 暴力と紛争の〝集団心理〟 社会心理学の視点から
- 人間の本性としての集団性 集団生活が暴力と紛争をもたらした 暴力嫌いの人間 暴力と紛争を引き起こす〝集団心理〟 鍵を握る「集団モード」 ⓐコミット型集団モード ⓑ生存戦略型集団モード ただし、単純な「集団=悪玉」論ではない 本書の構成 社会心理学の視点――状況が人間の行動を規定する あなた自身の物語 用語の整理
- 第Ⅰ部 内集団過程と集団モード
- 第1章 集団への愛は暴力を生み出すか?
- 愛国心と暴力 所属心としての集団アイデンティティ 集団アイデンティティはそれ自体で外集団への暴力を強めたりはしない [条件一]集団間紛争・競争状況のとき 集団間感情理論から見た紛争状況下の集団間攻撃性 集団のための自己犠牲的攻撃――アイデンティティ融合 内集団のために戦う戦士たち アイデンティティ融合における集団間紛争・競争状況の重要性 [条件二]集団アイデンティティの下位側面のうち、優越性・支配性が前面に出たとき 優越視のもつ過敏さが攻撃を引き起こすとき 条件一、条件二に共通する集団アイデンティティのあり方
- 第2章 集団への埋没と暴力 没個性化、暴動
- 集団への埋没と匿名性が引き起こす暴力 没個性化の心理メカニズム①――自己意識の低下による抑制の喪失 こんなところでも没個性化が暴力と反社会性を引き起こす 逆に集団の匿名性が暴力を低下させるとき 没個性化の心理メカニズム②――「集団モード」と集団規範への同調 暴動=集団モードによる集団間紛争 インターネットと匿名性
- 第3章 「空気」が生み出す集団暴力
- 「空気」と「権威」と集団暴力 ミルグラム実験に見る権威への服従 服従実験の追試 服従が強くなるとき、弱くなるとき テレビ番組の「空気」と服従 服従を生み出す「集団モード」 命令から始まり、自発的に攻撃する スタンフォード監獄実験 二〇〇〇年代の監獄実験の追試――BBC監獄実験 スタンフォード監獄実験の現代的解釈――暴力的集団モードの付与 アブグレイブ刑務所 現代日本社会における「いじめ」と「空気」と「悪ノリ」と 不服従と抵抗のためにはどうすればよいのか
- 第4章 賞賛を獲得するための暴力 英雄型集団暴力
- 集団中で私の立ち位置はどうなっているのか――生存戦略型集団モード 集団内生存戦略の二側面――賞賛獲得と拒否回避 ①賞賛獲得のための英雄型集団暴力と、②拒否回避のための村八分回避型集団暴力 Part 1. 賞賛獲得を求めた英雄型集団暴力――攻撃者が賞賛されるとき 賞賛獲得を求めた暴力 戦士として戦うことは進化的に有利だったから? 非行集団における賞賛獲得を求めた集団暴力 タフで粗暴な男らしさの規範が暴力を生み出す――名誉の文化 名誉の文化で暴力的だという評判が必要な理由 名誉の文化と戦争 現代日本における英雄型集団暴力
- 第5章 拒否を回避するための暴力 村八分回避型集団暴力
- Part 2:拒否回避を求めた村八分回避型集団暴力 攻撃に参加しない「非国民」が罰せられるとき 拒否回避が集団暴力を引き起こすとき ⓐ本心ではない差別の表明 空気の読み間違いが差別や暴力を生むとき ⓑ内集団ひいき ただし、内集団ひいき≠外集団攻撃 ⓒ集団暴行殺人、ジェノサイド、名誉殺人の事例 日本人は拒否回避志向がとくに強い 賞賛獲得型と拒否回避型とは混在しうる 排斥後に引き起こされる集団暴力
- 第Ⅱ部 外集団への認知と集団間相互作用過程
- 第6章 人間はヨソ者をどう見ているのか? 偏見の科学
- 私は「たけのこ派」、奴らは「きのこ派」 対立的集団間関係の捉え方の基本原理――内集団=good、外集団=bad 社会的カテゴリー化による同化と対比 ステレオタイプ――「枠」をはめて非難する 目の色で差別してみると…――『青い目 茶色い目』 偏見はなかなか修正できない――確証バイアスとサブタイプ化 現代的な差別――奴らは不当な特権を得ているのか? 偏見が表出されるには正当化と非抑制が必要――偏見の正当化抑制モデル 「自己中心的」ならぬ「自集団中心的」な歪んだ判断 認知バイアス①――究極的帰属エラー 認知バイアス②――反発的低評価 認知バイアス③――敵味方分断思考
- 第7章 「敵」だと認定されるヨソ者 脅威と非人間化
- 脅威 「外集団=怖い」? 外集団を見ると恐怖を感じる脳部位が活動する 脅威の二側面――現実的脅威と象徴的脅威 保守主義者の脅威過敏性 脅威が引き起こす防衛的先制攻撃 黒人やイスラム教徒は〝怖い〟から撃たれやすい――狙撃手バイアス 敵なら殺してもよい?――非人間化 非人間化と暴力反応 集団間攻撃と非人間化 非人間化はいかにして危害を促進するか? 抑制の低下と慢性化 外集団は人間らしい感情をもたない――人間性希薄化 露骨な形の非人間化
- 第8章 報復が引き起こす紛争の激化
- 集団間関係において生じる報復とは? 代理報復の連鎖による集団間紛争の拡大 集団間代理報復の実験枠組み 初対面集団での実験結果 集団間代理報復のメカニズム メカニズム①――「社会的カテゴリー化」というコミット型集団モードからの説明 ①内集団同一視(内集団アイデンティティ)――被害者個人から内集団全体へ ②外集団実体性知覚――加害者個人から外集団全体へ 内集団同一視と外集団実体性知覚 メカニズム②――「英雄になろうとして報復する」という生存戦略型集団モードからの説明 ①内集団観衆の効果 ②仲間から協力を期待される 拒否回避と集団間代理報復の関係性に関して 被害〝感〟の重要性 被害者は暴力の見え方自体が異なる
- 第Ⅲ部 暴力と紛争の解消を目指して
- 第9章 どうやって関わり合えばよいのか? 暴力と紛争の解消を目指して
- 集団暴力を解消・低減する二つのアプローチ 1:集団間アプローチ 1a:集団間接触 直接会う必要さえない? 集団間接触はなぜ効果的なのか 1b:視点取得と共感 視点取得はなぜ効果的か? 知能の時代的上昇に伴う偏見の低減 1c:共通目標と共通上位集団アイデンティティ シェリフのサマーキャンプ実験 共通上位集団アイデンティティへの再カテゴリー化 自分たちはともに被害者であり、加害者でもある 共通上位集団の難しさ ①劣勢集団であるマイノリティ側は共通上位集団を好まない ②不平等が覆い隠される 二重アイデンティティ 2:集団内アプローチ 2a:反暴力的規範・風土の変革 反暴力的集団規範/社会規範を社会にいかに醸成するのか? 外集団への偏見と規範 偏見を低減させる規範変容 2b:多様性(ダイバーシティ)と包摂性(インクルージョン) 今から紛争と暴力がより減少した未来をいかにつくっていくか?
- あとがきに代えて
- 文明化に伴う暴力低減の時代潮流 規範と価値観の時代に伴う変化 暴力低減の潮流を止めないために
- 図表の出典
- 注・文献
- 人名索引
- 事項索引
Mのコメント(言語空間・位置付け・批判的思考)
ここでは、対象となる本の言語空間がどのようなものか(記述の内容と方法は何か)、それは総体的な世界(言語世界)の中にどのように位置付けられるのか(意味・価値を持つのか)を、批判的思考をツールにして検討していきたいと思います。ただサイト全体の多くの本の紹介の整理でアタフタしているので、個々の本のMのコメントは「追って」にします。