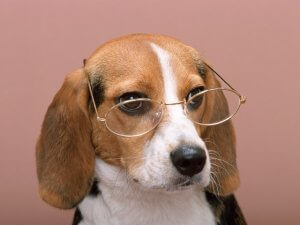書誌

人間とは何かという問いに、生物学から認知科学までを駆使して詳細に解き明かそうとする本格的な論考。理解するのは容易ではない、岩登り登山級。
要旨と目次
主要な主張
本書は、人間の存在を生物的、神経生物的、認知的、意識的という相互に作用する4つの基本的な「存在次元」の複合体として再定義する包括的理論を提案する。従来の「自己」や「人格」といった心理学的概念を、科学的実体として扱うことの曖昧さと問題点を批判し、より厳密な生物学的・進化的基盤を持つ次元的枠組みを提示する。これらの4つの次元は階層構造をなし、意識は認知に、認知は神経生物学に、神経生物学は生物学に依存する。
本書の中心的主張は、人間の意識的経験が、脳の非意識的(より正確には前意識的)な認知プロセスから生じる解釈、すなわち「物語(ナラティブ)」であるという点にある。この物語は、ワーキングメモリ内で構築されるメンタルモデルから生成される。メンタルモデルは、言語に依存しない抽象的な神経コード(メンタリーズ)を用いて感覚情報、記憶、スキーマ、目標などを統合し、一貫した経験を生み出す。
進化論的視点から本書は、生命の起源から人間の意識の出現までをたどり、各次元が進化過程でどのように構築されたかを詳述する。特に行動制御における、単純な刺激反応(モデルフリー)から内的メンタルモデルを用いる柔軟な目標指向行動(モデルベース)への移行を重要な進化的段階と位置づける。最終的に、意識は単一の謎ではなく、これら相互に連結した次元の活動を統合する脳の物理的プロセスとして科学的に解明可能であると結論づける。
1. 人間存在の再定義:従来の概念の批判と新たな枠組み
本書は、人間の本質を理解するための伝統的概念である「自己(self)」と「人格(personality)」に内在する問題点を指摘し、これに代わる概念的枠組みとして「存在の四次元」を提案する。
1.1. 「自己」と「人格」概念の限界
長らく哲学、心理学、神経科学の中心的な主題であった「自己」や「人格」は、科学的な実体として扱うには致命的な欠陥があるとされる。
- 定義の曖昧さ:「自己」や「人格」が具体的に何を指すのかについて専門家の間で一致が乏しい。それらは実体というより多様な心理現象を包括するラベルに過ぎない。
- 具象化の問題:言葉の存在を根拠に脳内にそれを担う実体(行為主体)が存在すると誤認するリスクがある。トーマス・メッツィンガーの指摘の通り、「自己を持つ人や自己である人など、かつて一度も存在したことがない」。
- 文化的偏り:現行の概念は主にヨーロッパ哲学に由来し、他文化的伝統を十分に反映していない。
- 科学的厳密性の欠如:心理学用語は日常語や常識的知見に依存しがちであり、これが科学的進歩を妨げる一因となっている。人格心理学者ジャック・ブロックは「性急であいまい、そしていい加減な用語法」が思考を支配していると警告している。
1.2. 分離脳研究からの洞察:物語る脳
著者がマイケル・ガザニガの指導下で行った分離脳患者ポール(P.S.)の研究は、脳が行動や経験を理解するために物語を構築するという考えの起点となった。
- 右半球の自己認識:ポールの右半球に「あなたは誰?」と尋ねると、彼の左手(右半球支配)はスクラブルの駒で「Paul」と綴った。右半球にも自己の感覚が存在する可能性を示唆する。
- 二つの異なる目標:ポールの左半球(発話可能)は将来の目標を「設計者」と語り、右半球は「カー・レーサー」と綴った。同一の脳から二つの異なる答えが出た。
- 解釈者(インタープリター)機能:左半球にニワトリの爪を、右半球に雪景色を見せてから絵を選ばせると、右手(左半球支配)はニワトリを、左手(右半球支配)はシャベルを選んだ。理由を尋ねると左半球は「ニワトリ小屋を掃除するにはシャベルが必要です」と答え、右半球の行動を自らの知識に合わせるストーリーを構築した。
この研究は、人間がストーリーを紡ぐことで自己と世界を理解する「解釈者」概念を生み、意識的理解が非意識的プロセスから生じる解釈、すなわち物語であるという本書の核心的主張の基礎となった。
1.3. 新たな枠組み:存在の四次元
本書は「自己」や「人格」に替えて、人間を4つの基本的存在次元の複合体として特徴づける。これらの次元は進化史を反映し、現在の存在様式を説明する。
| 存在次元 | 説明 |
|---|---|
| 生物的次元 | すべての有機体に共通する、生命維持の基本プロセス(代謝、複製など)を含む次元。 |
| 神経生物的次元 | 動物に特有の、神経系によって身体機能や行動が制御される次元。 |
| 認知的次元 | 外界の内的表象(メンタルモデル)を構築し、思考や計画を行う能力を持つ動物が属する次元。 |
| 意識的次元 | 自己や世界を主観的に経験する能力を持つ、一部の認知的有機体が属する次元。 |
| これら4つの次元は階層的かつ相互依存的である。意識は認知に、認知は神経生物学に、神経生物学は生物学に依存する。ある瞬間の4次元の統合状態は「次元のアンサンブル」と呼ばれ、生涯を通じて動的に変化する。 |
2. 四つの存在次元の詳細
2.1. 生物的次元:生命の基盤
生物的次元は他のすべての次元の前提条件であり、生命そのものの基盤を成す。
- 生命の定義:生命は非物質的な力ではなく、代謝と複製という物理的プロセスによって定義される。クロード・ベルナールの「内部環境(milieu intérieur)」の安定性、すなわちウォルター・キャノンが命名した「ホメオスタシス」が生命維持の鍵である。
- 有機体の特性:有機体は自己生産、自己組織化、自己維持の3つの特徴を持つ。その統合性は遺伝的等質性と、免疫系などによる構成要素間の凝集力によって保たれる(トーマス・プラデュの視点を含む)。
- 身体の二重性(ローマーの説):古生物学者アルフレッド・ローマーは脊椎動物の身体を機能的に二つの側面に分けた。
- 体壁的(Somatic)動物:骨格筋を中心に外界との相互作用(行動)を担う。
- 内臓的(Visceral)動物:平滑筋を中心に消化・代謝などの内部機能を担う。
この二重性は神経系の組織を理解する上で基礎的原理となる。
2.2. 神経生物的次元:行動の制御
神経系の進化により動物は単なる生物的存在を超えた神経生物的存在となった。
- 神経系の進化:神経系は遠隔の細胞間で迅速な通信を可能にし、迅速かつ精密な行動制御を実現した。その起源は刺胞動物(クラゲなど)の神経網に見られ、左右相称動物の出現とともに集中化(脳の形成)が進んだ。
- 非認知的行動制御:神経生物的次元の行動は主に柔軟性の低い自動的反応からなる。
- 反射:特定刺激に対する先天的な運動プログラム。
- 固定的動作パターン:採餌、防御、生殖など種の存続に不可欠な複雑な生得的行動(「サバイバル回路」に依存)。
- 習慣:刺激と反応の連合(S-R連合)が強化学習で形成される後天的自動行動。大脳基底核の背側線条体が中心的役割を担う。
- 神経系の二重性:ローマーの体壁的/内臓的区別は神経系にも適用できる。神経系の主たる機能は行動(体壁的)と代謝恒常性(内臓的)の両面を制御することである。
- 「三位一体脳」仮説の批判:ポール・マクリーンの爬虫類脳・旧哺乳類脳(辺縁系)・新哺乳類脳(新皮質)という三層モデルは、現代の進化学的知見と一致しない。脳は新部位が単純に古部位の上に追加されるのではなく、既存構造が拡張・緻密化することで進化した。
2.3. 認知的次元:メンタルモデルの構築
一部の動物は、非認知的刺激反応に加え、内的表象を用いて世界をモデル化する認知能力を進化させた。
- 認知の定義:認知とは、外界に関する内的表象を用いてメンタルモデルを構築し、それに基づいて思考、計画、意思決定を行う能力である。これにより、現実でリスクを負うことなく行動の選択肢を心の中でシミュレートできる。
- モデルフリー vs. モデルベース:
- モデルフリー制御:過去の経験に基づく刺激—反応の連合(習慣など)に依存する、計算コストの低い遡及的制御。神経生物的次元に相当する。
- モデルベース制御:目標の現在価値や状況構造に関するメンタルモデルを用いて柔軟に意思決定する、計算コストの高い未来指向的制御。認知的次元に相当する。
- 認知の進化:モデルベース認知は、哺乳類と一部の鳥類において、高い代謝率を維持するための効率的な採餌戦略として進化したと考えられる。両者は内温性で大量のエネルギーを消費するため、柔軟な計画能力が生存に有利となった。
- 認知を支える脳:
- 霊長類以外の哺乳類:目標指向的行動は背内側線条体、前頭前皮質(PFC)の中間領域(前辺縁皮質など)、扁桃体、海馬などが連携するネットワークに依存する。
- 霊長類:感覚情報を高度に統合し、ワーキングメモリの実行機能を担う「顆粒PFC」(特に外側PFCと前頭極)が発達し、抽象思考、マルチタスク、階層的推論を可能にした。
- 人間:顆粒PFC、特に前頭極がさらに拡張・特殊化し、言語能力と結びつくことで再帰的思考、心的時間旅行、精緻な心の理論などの独自の認知能力を支える。
2.4. 意識的次元:主観的経験の生成
意識的次元は、自己と世界を主観的に経験する能力であり、本書理論の頂点をなす。
- 意識への科学的アプローチ:本書は意識を非物理的な「ハードプロブレム」としての哲学的神秘主義から切り離し、脳の物理的プロセスとして科学的に解明可能な対象と見なす。
- 高次理論(HOT)の支持:意識は低次の感覚情報が単に存在するだけ(一次理論)で生じるのではなく、その情報がPFCにおいて認知的に「再表象/再記述」されることで生じる、という高次理論(HOT)を採用する。
- 意識の三種類(タルヴィングに基づく):意識的経験は基盤となる記憶の種類に応じて三つに分類される。
- アノエティック意識:手続き記憶に基づく、非認識的な「知っている」という感覚。経験の辺縁的・背景的質を提供する。
- ノエティック意識:意味記憶に基づく、事実や概念に関する意識。世界についての客観的知識の経験を含む。
- オートノエティック意識:エピソード記憶に基づく自己認識的意識。過去を追体験し未来を想像する「心的時間旅行」を可能にする。
- 意識の生成メカニズム:階層的マルチステートHOT
意識的経験の創発:このアモーダルな物語が意識的経験そのものである。物語の内容(意味記憶優位ならノエティック、エピソード記憶優位ならオートノエティック)がその瞬間の意識内容を決定する。発話や行動は同じ物語から派生する並行的出力である。
このモデルによれば、意識は単一のプロセスではなく、脳の複数階層にわたる動的相互作用から創発する物語であり、それによって私たちは統合された自己感を維持している。
メンタルモデルの構築:感覚情報、記憶、スキーマ、目標、身体状態などの多様な低次状態がPFC(特に顆粒PFC)で前意識的なワーキングメモリ・メンタルモデルとして統合される。
物語(ナラティブ)の生成:このメンタルモデルは、モード非依存の抽象的神経コード、すなわち「メンタリーズ」を用いて、現在の瞬間に関する前意識的な「物語」を出力する。
目次
- まえがき
- はじめに―あなたは誰?
- はじめに
- 宴の内容
- Ⅰ 人間の存在次元
- 1 人間とは何か?
- 前説
- 何を探しているのかがわからなければ、何も見つけられない
- 私たちの存在次元
- 2 「自己」を疑う
- 前説
- 自己の誕生
- 科学的な自己
- 「自己」批判
- 創発する自己
- 3 人格
- 前説
- フロイトとフロイト派
- 行動としての人格
- 人間性心理学
- 特性と気質
- 状況的な人格
- 身体化
- 流動的な人格の概念
- 人格/自己を見直す
- 4 たかが言葉、されど言葉
- 前説
- 心理学の用語
- 名づけによる説明
- 主体性という工作員
- 個人化された身体や脳
- 5 四つの存在次元
- 前説
- 四階層に統合された存在様式
- 存在論的モード
- その瞬間の四つの次元が次元のアンサンブルを形成する
- なぜわざわざ?
- Ⅱ 生物的次元
- 6 生命の秘密
- 前説
- 生物
- 生物学につきまとう生気論
- 内部環境
- 生命の起源
- 今日における生気論の残滓
- 7 身体
- 前説
- 有機体
- 生物的個体としての有機体
- 生物個体の再考
- ダーウィン的個体
- 生理的個体――統合された代謝活動
- 化学反応のセットとしての有機体
- 有機体は変化しつつも同一性を保つ
- 8 生物的存在の二重性
- 前説
- ローマーの身体二重説
- ローマーの用語について
- Ⅲ 神経生物的次元
- 9 神経が必要だ
- 前説
- 驚異的な移行
- 動物的生命
- 神経系の構成要素
- 相称的な身体は神経網以上の何かを必要とした
- カンブリア爆発
- 10 脊椎動物とその神経系
- 前説
- 後口動物と脊索動物の出現
- 脊椎動物の多様化
- 脊椎動物の脳
- 前脳をめぐる愚行――脳の進化に関する神話
- 哺乳類の前脳は実際にはどう進化したのか
- 11 ローマーによる再構成
- 前説
- 神経系の再設計
- ローマーの説を語り直す
- 12 内臓学
- 前説
- 内臓的末梢
- 内臓脳
- 内臓ループ
- 内臓の状態
- 覚醒
- 内臓反射は変わりうる
- 内臓組織を意志の力でコントロールできるのか?
- 13 行動
- 前説
- 感知
- 行動
- 反射
- 種特有の動作パターン
- 習慣
- 行動と心理の結びつき
- Ⅳ 認知的次元
- 14 外界の内化
- 前説
- ダーウィン流心理主義から刺激と反応の心理学へ
- 抵抗
- スキーマ
- 革命か進歩か
- 15 認知とは何か?
- 前説
- 認知と意識
- 人間における行動制御の三つのクラス
- 認知とワーキングメモリー
- 認知と記憶
- 人間の認知に対する二重システム/二重プロセスアプローチ
- システム1 非認知的で非意識的な行動制御(神経生物的次元)
- システム1 非認知的で非意識的な行動制御(神経生物的次元)
- ・反射 ・直観 ・パブロフ型条件づけ反応 ・習慣
- システム1 非認知的で非意識的な行動制御(神経生物的次元)
- システム2 認知的で非意識的な行動制御(認知的次元)
- ・非意識的なワーキングメモリー ・非意識的な熟慮 ・非意識的な推論 ・非意識的な直観
- システム3 認知的で意識的な行動制御(意識的次元)
- ・意識的なワーキングメモリー ・意識的な熟慮 ・意識的な推論
- システム1 非認知的で非意識的な行動制御(神経生物的次元)
- 人間の二重システムアプローチを再考する
- 動物における行動制御の二重システム
- 16 メンタルモデル
- 前説
- メンタルモデルと推論
- メンタルモデルと目標指向的行動
- マップ、モデル、一般的な認知のフレームワーク
- 17 モデルベースの認知の進化
- 前説
- 非哺乳類は認知的な動物なのか?
- なぜ哺乳類と鳥類なのか?
- ただ一つのモデル
- 18 心のなかで採餌する
- 前説
- 採餌の重要性
- メンタルサーチ
- 19 認知的な脳
- 前説
- 初期の哺乳類の前脳
- 霊長類以外の哺乳類におけるモデルベースの行動制御を司る脳のメカニズム
- 前頭前野革命
- 霊長類のワーキングメモリーの基盤をなす顆粒PFC
- 霊長類におけるモデルベースの目標指向的行動を司る脳のメカニズム
- 人間のPFCは特別か?
- 大型類人猿はどうか?
- 人間の認知の神経基盤についての要約
- Ⅴ 意識的次元
- 20 意識は謎なのか?
- 前説
- 哲学のハードプロブレム
- 論理の限界
- 科学と魂
- 意識の物理的な説明によって何がもたらされるのか?
- 心理を行動に還元する
- 心理を神経メカニズムに還元する
- 意識研究の復活
- 21 意識の種類
- 前説
- 心的状態意識
- 私がHOTに与する理由
- HOTに対する批判
- HOTのバリエーション
- 車輪の再発明
- 感覚中心アプローチの再考
- FOTやHOTと存在次元
- 22 意識を意味あるものにする
- 前説
- 意味ある意識的経験は記憶を必要とする
- 視点を覆す
- 意識の階層的マルチステート理論の構成要素
- 再帰性、一斉送信、高次の気づき
- 意識に対するPFCの寄与を紐解く
- PFCと意識に関する誤解
- 23 事実認識と自己認識
- 前説
- 顕在記憶のタイプ
- 顕在的な意識の内容は顕在記憶によって可能になる
- ノエシスとオートノエシスの基盤をなすメタ認知プロセス
- オートノエシスにおける「自己」
- ノエシスとオートノエシスの基盤をなす脳のメカニズム
- 過去、現在、未来のエピソード
- 前頭前皮質、デフォルト・モード・ネットワーク、自己認識
- 記憶と意識の再考
- 24 非認識的意識
- 前説
- アノエシスの逆説
- アノエシスとアフェクト
- アノエシスと心や身体の状態の「所有」
- 深層学習
- 怖れや他の情動におけるアノエシスからオートノエシスへの移行
- アノエティックな状態はクオリアの身体的な顕現なのか?
- 25 動物の意識とは、どのようなものでありうるか
- 前説
- 方法論的な障害
- ダーウィンの科学的擬人主義の影響
- なぜ擬人主義がはびこるのか?
- 方法論的な障害を最小限に抑える方法
- 温血動物と冷血動物の意識
- 有感性(Sentience)と科学(Science)
- 26 自分自身や他者について語るストーリー
- 前説
- 物語る人生
- 物語の内容
- 物語は前意識的でアモーダルである
- メンタリーズ
- メンタリーズと脳
- メンタリーズによる物語の流れとその分流
- 認知、意識、エネルギー
- 難題を知る
- 心と機械――リトマス試験
- 私たちは私たちのニューロンであり、私たちのニューロンは私たちのものである
- 円環を閉じる
- 訳者あとがき
- 参考文献(一部)と読書案内
Mのコメント(言語世界・つながり・批判的思考)
コメントは、同著者の「情動と理性のディープ・ヒストリー: 意識の誕生と進化40億年史」を紹介しつつ作成しよう。両著とも主たる主張だけでも核心をついて思うが、細部の叙述も含め、フォローするのは大変だ。