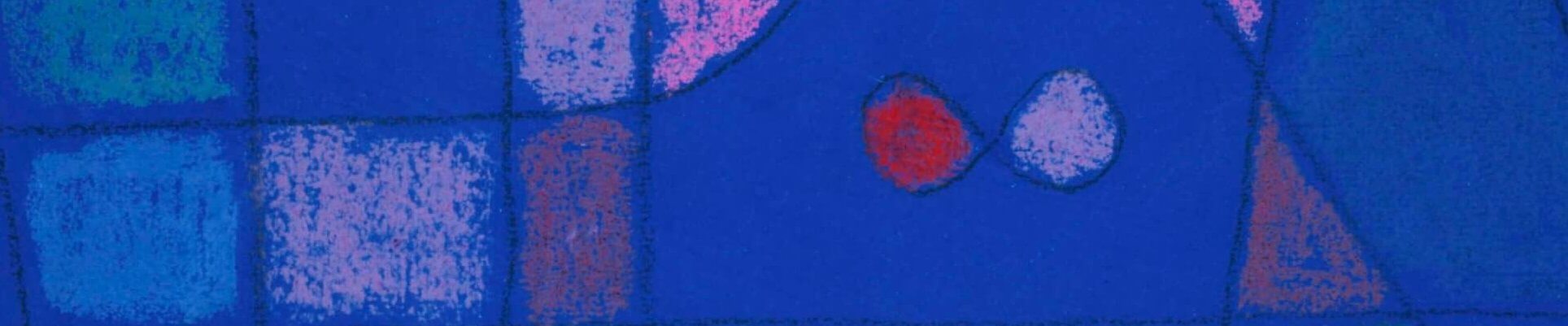「リーガルテック」を読む
著者:佐々木隆仁
デジタル社会の難問、病理に向き合う先日あった「シンポジウム 人工知能が法務を変える?」では、レクシスネクシスのトルコ人弁護士が「リーガルテック」という観点から、今後の弁護士業務のあり方を切り取っており、刺 ...
「シンポジウム 人工知能が法務を変える?」を聞く
2017年11月29日(水)、日弁連法務研究財団と、第一東京弁護士会総合法律研究所IT法研究部会共催の、標記のシンポジウムを聞いた。
登壇して話をしたのは、マイクロソフトのエンジニア、日本カタリスト ...
「プロフェッショナルの未来」を読む
この本「プロフェッショナルの未来 AI、IoT時代に専門家が生き残る方法」(The future of the profession)の ...
IT・AIの法律書を使う
IT・AI関係の法律書のうち、法律相談形式のもの、及び関係する事項について体系的に触れているもののうち、私の手許にあるものについて、その詳細目次を掲載しておきます。皆さんが直面している問題が、どういう位置づけになるの ...
「ビットコイン」を考える
「ビットコイン」(仮想通貨、暗号通貨)と、それを支える「ブロックチェーン」という技術が、大分前から喧伝されている。仮想通貨の取引所の倒産(2014年)、分裂(2017年8月)といわれれば、それだけで怪しそうだと ...
「法のデザイン」を読む
著者:水野祐
若い世代の意欲的な試みこの本は、少し前に、若い弁護士が書いた法のあり方について論じた珍しい本だと思い、紙本を買ったが、なんせ、文字が小さくてとても読む気にならず、放置していた(私の老眼というより「本のデザイン ...
基本から考える個人情報保護法(その1)
最近、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」)に関して検討した事案があり、2017年5月30日から改正保護法が全面施行されたこともあるので、改めて保護法について基本から考えてみることにした。IT、AIに関する法務のか ...
2004年に私が考えていた「ITが弁護士業務にもたらす影響」
2004年に、日弁連の弁護士業務改革委員会が刊行した「いま弁護士は、そして明日は?」という本に、当時、同委員会の副委員長としてIT部会長であった私は、「ITが弁護士業務にもたらす影響」という論考を執筆してい ...
弁護士として「AIと法」に踏み出す
最近、AIに関する話題が広く喧伝されている。しばらく本屋さんに行かないと、「人工知能」や「ディープラーニング」に関する新しい本が充ち溢れていてびっくりしてしまう(さすがに、Kindle本は、少し遅れる。)。ネッ ...
太陽光発電設備を規制する条例を作る
私は、南アルプスや八ヶ岳に囲まれた自然豊かな某市の市議会議員の方々から、同市内で今後も増え続けることが見込まれる太陽光発電設備について、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特 ...