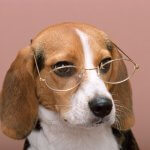<AI時代の質問力:岡瑞起>を読む
この投稿は、固定ページの「問いは世界を創造する:問題解決と創造」のために作成した記事の一部を投稿したものです。
現代の問いープロンプティングプロンプティングは付き合い方が少し難しいプロンプティングとは、生成AIに指示・質問 ...
問いは世界を創造する
「問い」は、世界を理解し、働き掛け、変えていく上での、すべての出発点であり、暫定的に得た「回答」からの折り返し点でもある。その繰り返しが、世界の理解及び問題解決と創造に結びつく。この過程を「問いは世界を創造する」と捉 ...
知覚力・観察力が世界を拓く
知覚力・観察力は、「問い」を充実させる基盤となる。
その知覚について論述した後記の「観察力を磨く」、「知覚力を磨く」という似通った本がある。いずれも絵画の研究者、愛好者として、基本に絵画を据え、知覚力・観察力を磨 ...
生成AIと共に
これまでPC→IT→DX(DS)の流れに、適宜AIが絡み、デジタル技法が進展してきた。ただ問いを具体的に展開する「推論、アイデア、リサーチ」は、人手(脳)が行っていたので、これを十全に利用するには困難 ...
<問いの編集力:安藤昭子>を読む
「問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する:安藤昭子」は、故松岡正剛のスキーム(例えば「知の編集工学」)と重なる部分があるが、文化・教養に関わる問題をきちんと整理していて、格好いいし、応用範囲も広いので参考になる。
<知的生産の技術:梅棹忠夫>を読む
まず手始めに「知的生産の技術」の「目次と要約」を生成AIを利用して作成してみた。少し長すぎるが、この本を振り返り、新たな領域を解体するには悪くないできだ。ただこれを見る人は参考に止めてほしい。私は「要約」の内容についてはざ ...
問いは世界を創造する:生成AIと共に
「問い」は、世界を理解し、変えていく上でのすべての出発点であり、折り返し点でもある。この過程を「問いは世界を創造する」と捉えよう。「問いは世界を創造する」というのはいささか大仰な物言いだし、「問題解決と創造_総論」 ...
七面山に登る
2024年10月28、29日に七面山に登った。七面山は二百名山で1992メートルある。七面山の山頂近く(1700メートルぐらい)に「敬慎院」という日蓮宗の寺院があり、1日目は表参道を登ってそこに泊り、2日目に山頂を往復し北参 ...
情報へのアクセスとリサーチ
様々な情報源にアクセスしリサーチする方法をまとめておこう。
リサーチする前提には、当然、問いがある。「リサーチ論」で挙げる本は緻密なリサーチ方法を展開しているが、つまらない「問い」のために力 ...
<バリ山行>を読む
一見すると、何だ?と思うタイトルだが、バリが、バリエーションルートだと分かれば、山行に容易に結びつく。だがこの作品が、2024年の芥川賞を受賞したと聞くと、ほほー ...