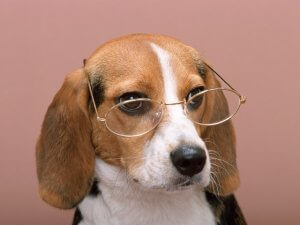Mのコメント
序
知覚力・観察力は、「問い」を充実させる基盤となる。
その知覚について論述した後記の「観察力を磨く」、「知覚力を磨く」という似通った本がある。いずれも絵画の研究者、愛好者として、基本に絵画を据え、知覚力・観察力を磨く議論を展開する。レオナルド・ダ・ヴィンチや、シャーロック・ホームズに注目する点も重なっているので混乱してしまう。そこでGNoteに次の質問をしてみた。回答の質はなかなかのものだ。ただし、細部まで正確とはいえないので、興味のある方は原本にあたって確認されたい。
あと、「シャーロック・ホームズの思考術:マリア コニコヴァ」という本も類似した内容を持っていたと思うので、追って紹介しよう。
質問
二つのソースは、それぞれ知覚力と観察力を鍛えて、様々な問題に対処すべきであるということを共通して主張していると考えられます。二つのソースの、知覚力、観察力をどのように鍛えるべきかという方法や手段についての主張について、共通する点、異なっている点を挙げてください。
回答
- 共通点
- 注意を払うことの重要性:「知覚力を磨く」では、意識的に関わることの重要性が述べられています。同様に、「観察力を磨く」でも、注意深く観察することが重要視されています。
- 客観性と主観性の区別:「知覚力を磨く」には、先入観にとらわれない柔軟な思考が推奨されています。また、「観察力を磨く」では、先入観を排除し、客観的な事実に基づいて判断することが重要視されています。
- 五感を活用すること:「知覚力を磨く」では、五感を通じて得た情報を重視することが示唆されています。また、「観察力を磨く」でも、五感を活用した観察が推奨されています。
- 全体像と詳細の把握:「知覚力を磨く」では、全体像を捉えつつ細部を観察することが重要であると述べられています。同様に、「観察力を磨く」でも、全体を捉えつつ、細部に注意を払うことが重要視されています。
- 相違点
- 絵画の利用:「知覚力を磨く」では、絵画を観察することを通じて知覚力を養うという視点が強調されています。一方、「観察力を磨く」でも名画読解というタイトルではあるものの、絵画に限らず様々な対象の観察が視野に入っています。
- 知識と経験の重要性:「知覚力を磨く」では、知識のインプットと知覚の出力の重要性が述べられています。また、「観察力を磨く」では、過去の経験や知識が観察に影響を与えることが示唆されています。
- 観察の目的:「知覚力を磨く」では、問題解決や意思決定に役立つ知覚力を養うことが目的とされています。一方、「観察力を磨く」では、より良い人生を送ることを目的とした観察力の向上が強調されています。
- 具体的な訓練方法:「観察力を磨く」には、対象を詳細に記述する訓練や、五感を活用した観察など、具体的な方法が提示されています。一方、「知覚力を磨く」では、観察と解釈を分離することや、先入観にとらわれない柔軟な思考など、より抽象的な概念が強調されています。
- まとめ
- 両方のソースは、注意を払い、客観的に観察し、五感を活用することの重要性を共通して主張しています。しかし、「知覚力を磨く」は絵画の利用を強調し、問題解決に役立つ知覚力を養うことを目的としているのに対し、「観察力を磨く」はより広い対象を視野に入れ、人生を豊かにするための観察力を高めることを目的としています。また、「観察力を磨く」の方が、より具体的な訓練方法を提示しているという違いもあります。
<知覚力を磨く:神田 房枝>の要約と目次
書誌 知覚力を磨く――絵画を観察するように世界を見る技法:神田 房枝(ダイヤモンド社)(2020年10月)
各章の要約
はじめに 観ているつもりで、見えていない私たち
この章では、私たちが日常的に「観ているつもり」になっているだけで、実際には見えていないことが多いという問題提起から始まる。知覚がいかに重要か、そしてそれを磨く必要性が述べられている。
第1章 すべては知覚からはじまる――あなただけが観ている世界
知覚は、単なる情報の受容ではなく、独自の解釈を加えるプロセスであると定義されている。同じものを見ても、人によって知覚が異なる例として、「半分水が入ったグラス」の解釈の違いが挙げられている。また、知覚は固定されたものではなく、経験や知識によって変化することも示唆されている。ピーター・ドラッカーの言葉を引用し、知覚がすべての始まりであると強調している。
第2章 観察する眼――知覚力の源泉
知覚力を磨くための最も確実な方法として、観察が挙げられている。レオナルド・ダ・ヴィンチを例に、詳細な観察がいかに革新的なアイデアにつながるかを示している。観察は、単に視覚的な情報を得るだけでなく、知覚と学習・経験から得た既存の知識を統合し解釈することであると説明されている。
第3章 見えない世界を観る――マインドアイの系譜
ここでは、マインドアイ、つまり心眼の重要性が強調されている。マインドアイは、視覚的なイメージを想像し、それを基に思考する能力であり、創造性や問題解決に不可欠である。アインシュタインの例を挙げ、視覚的思考(ビジュアルシンキング)がいかに重要かを示している。
第4章 何を観るか――絵画を観察するように世界を見る技法
絵画を観察することは、世界を見るための訓練になると述べられている。絵画は、観察の対象として最適であり、 detailに目を向け、全体像を把握する能力を養うことができる。また、絵画の背後にある文化、歴史、人間などの要素を考慮に入れることで、より深い理解が得られると説明されている。
第5章 どう観るか――知覚をブーストする4つの技術
知覚を向上させるための具体的な技術が紹介されている。
- 全体図を捉える
- 先入観を捨てる
- contextを考慮する
- 関連付ける力を高める
ドラッカーが日本の美術を推奨した理由として、水墨画を例に挙げ、全体と部分の関係を理解することの重要性が述べられている。
第6章 知覚する組織へ――リベラルアーツ人材の時代
組織における知覚の重要性が論じられている。リベラルアーツ教育を受けた人材は、多様な視点から物事を捉え、組織全体の知覚力を高めることができると説明されている。企業がリベラルアーツを重視する背景には、AI時代において、人間만이 가능한 능력(共感性、創造性、コミュニケーション能力)がより重要になっていることがある。
終章 さあ、曖昧な世界で「答え」をつくろう――The Age of Perception
現代社会は曖昧で不確実な状況に満ちており、固定された知識や思考だけでは対応できないと述べられている。知覚を磨き、曖昧さを受け入れることで、新たな問題解決や意思決定が可能になると結論付けている。
おわりに 太古に「未来」を知覚する
古代の洞窟壁画を例に、人間は太古の時代から知覚を通じて未来を予測し、生存してきたと述べている。現代社会においても、知覚を磨くことで、不確実な未来に対応できると主張している。
全体の要約
本書は、知覚がいかに重要であるか、そして知覚力を磨くための方法を解説する書籍である。現代社会は、情報過多で変化が激しく、過去の知識や経験だけでは対応できない状況に直面している。このような時代において、重要となるのは、表面的な情報に惑わされず、本質を見抜く力、つまり知覚力である。
知覚とは、単純な情報受容ではなく、個人的な解釈を加えるプロセスである。同じものを見ても、人によって異なる解釈が生まれるのは、知識や経験、価値観などが影響を与えるためである。したがって、知覚力を高めるためには、多様な観点から物事を観察し、自身の先入観や偏見を排除する必要がある。
本書では、知覚力を磨くための具体的な方法として、観察、マインドアイ、絵画鑑賞という三つのアプローチを提示している。観察は、事物を詳しく見て、細部に注意を傾けることである。レオナルド・ダ・ヴィンチのように、綿密な観察を通して、革新的なアイデアを創出した事例も紹介されている。マインドアイは、心の中でイメージを描き出し、それを基盤として思考する能力である。アインシュタインは、視覚的な思考を活用して、相対性理論を構想したと言われている。絵画鑑賞は、世界を見る新しい方法を学ぶのに役立つ。絵の中に隠された物語や背景を理解しようと努力することによって、世界をより深く理解することができる。
さらに、本書では、知覚力を向上させるための四つの技術も紹介している。
- 全体図を把握する。
- 先入観を捨てる。
- 文脈を考慮する。
- 関連付ける力を高める。
これらの技術を実践することで、断片的な視覚から脱却し、全体的かつ均衡のとれた視覚を確立することができる。
本書は、個人だけでなく組織にとっても知覚の重要性を強調する。AI時代には、共感能力、創造力、コミュニケーション能力といった人間固有の能力が一層重要になる。多様な背景を持つ人材を活用し、組織全体の知覚能力を高めることが競争力強化につながる。
本書は、固定観念と偏見に囚われず、周囲を注意深く観察し、新しいアイデアを創出する力、すなわち知覚力を養うことが不確実な時代を生き抜く上で不可欠だと主張している.
詳細目次
知覚力を磨く
はじめに 観ているつもりで、見えていない私たち
第1章すべては知覚からはじまる ——あなただけが観ている世界
私たちが見ている「個人的な世界」のポテンシャル
新しいものは「誰かの主観」から生まれる
「『すべてが何か違う』と感じるところを私は気に入った!」
「集められた知覚」が持つ爆発力
「グラスの水」からドラッカーが導き出した意味
主観的な決断は〝いい加減〟なのか?——LEGOのデータ分析
データ時代に問われるのは、マネジャーの「人間観」
「感じ方」を磨くと、「学び方」も磨かれる
知覚は「コントロール」できない——知覚と思考の差異
歴史を塗り変えた日本人の知覚——セイコーの「クオーツ革命」
思考力が優れているのに、なぜ活躍できない?
第2章観察する眼 ——知覚力の源泉
知覚力を磨く「最も確実な方法」とは?
なぜ「独学者ダ・ヴィンチ」は、圧倒的な業績を残せたのか?
『手稿』から見えてくる「知覚重視」の痕跡
「よく観ること」への異常なこだわり
「肉眼での観察力」が「アイディアを観る力」につながる
リベラルアーツとは「幅広い教養の習得」ではない
第3章見えない世界を観る ——マインドアイの系譜
私たちの眼は「検索モード」にとらわれている
「ゴリラ」を見落とすとき、何が起きていたのか?
「目的なく見る力」が価値を持ちはじめた
「発見」にとらわれない見方が「発見」を導いた
AIの眼はいまだに「サルと人間」を見分けられない
「人間の眼」と「機械の眼」の圧倒的な差
「知覚する脳」はコントロールできない——「見る」の弱点
最新脳科学とプラトンが見抜いた「真実をとらえる眼」
洞窟のなかで「見えないもの」を観てみよう
あなたのマインドアイは、どれくらい観えているか?
アインシュタインの「絵」で考える力
第4章何を観るか ——絵画を観察するように世界を見る技法
クロサワの圧倒的な「視覚的ストック」
「得体の知れない作品」を前にした美術史学者のように
ノーベル賞受賞者の9割以上が「アート愛好者」
経営者のアート収集は、単なる道楽ではない
生まれつき「絵を観るように」世界を見ている人たち
たった3時間で「診断する力」が13%向上する
ハーバード大も導入、アートを使った観察力トレーニング
なぜ絵画でなければならないのか——3つのメリット
「よく観た」と言える時間は、いったいどれくらい?
あなたの観察力を試してみよう
「細部をじっくりと観る」では不十分——ホームズの17段の階段
私たちの知覚力を奪う「敵」とは?
「ラベルなしに観る感覚」をつかむ
第5章どう観るか ——知覚をブーストする4つの技術
細部にとらわれない人は、眼球をどう動かしている?——技術①
マインドアイで「具体性に満ちた全体」をとらえる
ドラッカーが日本美術のコレクターだった理由
マネジャーは「水墨画」のように組織をとらえよ
複雑な世界に立ち向かう「組織的観察」——技術②
レクサスを生んだ「トヨタの観察」
ブラインドスポットには「宝」が眠る——技術③
御社は「周縁部での変化」を見落としていないか?
イノベーターは「見えないつながり」を観る——技術④
絵を観るだけで「関連づける力」が高まる
第6章知覚する組織へ ——リベラルアーツ人材の時代
共感力とは「自分の知覚を超える能力」である
「初対面の人の心」も知覚できるようになる
マッキンゼーの人材開発でも「絵画」が用いられている
なぜアップルの研修では、ピカソを観るのか?
オフィスに絵画を飾る意味
OODAループやデザイン思考も「観察」からスタートしている
どんな観察が「イノベーティブな組織」を生むのか?
トヨタ流・知覚力の磨き方——「現地現物」
クルマの組み立てがうまいのはどっち?——人間VS.ロボット
組織はリベラルアーツ化していく——ジョブズの予言
企業は「教養ある知識人」など求めていない
テクノロジー部署以外にも「スター」が隠れている
グローバル企業のトップに多い「リベラルアーツ専攻」
終章さあ、曖昧な世界で「答え」をつくろう ——The Age of Perception
おわりに 太古に「未来」を知覚する
<観察力を磨くエイミー E ハーマン>の要約と目次
書誌 観察力を磨く 名画読解:エイミー E ハーマン (早川書房)(2016年10月)
各章の要約
著者より・始まり
「知覚の技法」を教え始めて4年になる著者が、セミナーを通じて世界中の人々からアートに関する貴重な体験を聞き、それらを本にまとめた経緯が述べられている。本書は、事実に基づいた話に基づいており、可能な限り正確に記録されている。
第一部 観 察
観察の重要性と、観察を妨げる要因、そして観察力を磨くための方法が紹介されている。
人は見ようとする世界しか見ることができない。
先入観や固定観念にとらわれず、注意深く観察することの重要性が強調されている。
第一章 レオナルド・ダ・ヴィンチの力の秘密──大事なものを見る
レオナルド・ダ・ヴィンチの観察力に着目し、彼が科学と芸術の両方で優れた業績を残せた理由を探る。
ダ・ヴィンチは物事を注意深く観察し、その本質を見抜く能力に長けていた。
カギは、先入観にとらわれず、ものごとを注意深く見ることにある。
観察力を高めることで、問題解決能力や発想力が向上する可能性が示唆されている。
第二章 名探偵、参上──観察の技をマスターする
シャーロック・ホームズを例に、観察の技術を解説する。
ホームズは、観察によって得られた情報を基に、論理的な推論を重ね、事件の真相に迫っていった。
観察力を高めるには、意識的に物事を観察すること、そして得られた情報を分析し、解釈することが重要である。
観察の際には、先入観や固定観念を排除し、客観的な視点を持つことが不可欠である。
第三章 カモノハシと泥棒紳士──どうして人によって見え方がちがうのか
人の認識がいかに主観的であるかを考察する。
同じものを見ても、人によって異なる解釈をすることを紹介。
人の認識は、経験、知識、感情などによって大きく左右される。
先入観や偏見が認識に影響を与えることを示唆する。
客観的な認識を得るためには、自分自身のフィルターを理解し、それを意識的に排除することが重要である。
第四章 客室乗務員が無意識に行なうこと──客観的観察のポイント
客室乗務員が、安全を確保するために、無意識のうちに周囲を観察していることに注目する。
客室乗務員は、乗客の様子、手荷物、不審な行動などを観察し、異常を早期に発見しようとしている。
客観的な観察力を養うには、目的意識を持つこと、注意を払うこと、そして訓練を重ねることが重要である。
第五章 マヨネーズはどこに?──全体も細部も見る
全体と細部の両方を観察することの重要性を説く。
部分にばかり目を奪われると、全体像を見失ってしまう危険性がある。
全体を把握した上で、細部を観察することで、より深い理解が得られる。
観察力を高めるには、広い視野と細部への注意の両方を養う必要がある。
第二部 分 析
第六章 全周に目を配れ──あらゆる角度から分析する
物事を多角的に分析することの重要性を説く。
一つの視点だけでは、物事の本質を見抜くことは難しい。
異なる視点から分析することで、より客観的で正確な理解が得られる。
多角的な分析を行うには、知識、経験、発想力が必要である。
先入観にとらわれず、柔軟な思考を持つことが重要である。
第七章 私はなぜ、引き金を引いたのか──情報の優先順位
緊急時における情報の優先順位の重要性について、著者の経験を基に解説する。
人は緊急時には、冷静さを失い、適切な判断を下すことが難しくなる。
優先順位をつけることで、限られた時間の中で最も重要な情報に集中し、的確な判断を下すことができる。
情報の優先順位をつけるには、目的を明確にし、状況を正確に把握することが重要である。
第三部 伝 達
第八章 ワインの値段──コミュニケーションの不具合を防ぐ方法
コミュニケーションにおける誤解を防ぐための方法を、ワインの例え話を用いて解説する。
コミュニケーションにおいては、言葉だけでなく、非言語的な要素も重要であることを指摘。
相手の知識や経験を考慮し、適切な言葉を選ぶことが重要である。
誤解が生じた場合には、率直に意見を交換し、相互理解を深めることが大切である。
第九章 ビッグ・スー──厳しい現実を適切に伝えるには
困難な事実を適切に伝えるための方法を解説する。
事実を伝える際には、相手の感情に配慮し、共感の姿勢を示すことが重要である。
率直でありながら、思いやりを持って伝えることが大切である。
相手が事実を受け入れやすいように、段階的に情報を提供するのも有効である。
第四部 応 用
第一〇章 介護施設でストリップショー──生まれ持ったバイアスを克服する
先入観や偏見を克服することの重要性を説く。
人は誰でも、無意識のうちに先入観や偏見を持っている。
先入観や偏見にとらわれると、物事の本質を見誤ってしまう危険性がある。
先入観や偏見を克服するには、多様な視点を取り入れ、批判的思考を養うことが重要である。
第一一章 担架がないときはどうするか──不確かな状況に対応する方法
不確実な状況に対応するための方法を解説する。
状況を正確に把握し、利用可能な資源を最大限に活用することが重要である。
固定観念にとらわれず、柔軟な発想を持つことが大切である。
周囲の人々と協力し、知恵を結集することで、困難を乗り越えることができる。
終わりに──知覚の技法をマスターする
知覚の技法をマスターすることの重要性を改めて強調。
観察、分析、伝達の能力を高めることで、仕事や人間関係など、人生のあらゆる面で成功を収めることができると述べている。
知覚の技法は、訓練によって誰でも身につけることができる。
日々の生活の中で意識的に実践することで、観察力、分析力、伝達力を向上させることができる。
全体の要約
本書は、観察力、分析力、伝達力という3つの知覚の技法を総合的に解説し、それらを向上させるための方法を具体的に提示するものである。第一部では、観察の重要性を説き、観察を妨げる要因や観察力を磨くための方法を、レオナルド・ダ・ヴィンチやシャーロック・ホームズといった偉人の事例を交えながら解説する。第二部では、分析の重要性を説き、多角的な視点から分析する方法や情報の優先順位をつける方法を、事例を通して解説する。第三部では、伝達の重要性を説き、誤解を防ぐためのコミュニケーションの方法や困難な事実を適切に伝えるための方法を解説する。第四部では、先入観や偏見の克服、不確実な状況への対応といった応用的なテーマを扱い、知覚の技法を実践する方法を具体的に示す。
本書の特徴は、単なる知識の伝達に留まらず、読者が自ら思考し、実践することを促す点にある。事例や練習問題が豊富に盛り込まれており、読者は自らの知覚の癖や思考の偏りに気づき、改善するためのヒントを得ることができる。また、著者自身の経験や失敗談も率直に語られており、読者は親近感を持ちながら学ぶことができる。
本書は、ビジネス、教育、医療、人間関係など、あらゆる分野で役立つ知覚の技法を提供する。観察力、分析力、伝達力を高めることで、問題解決能力、意思決定能力、コミュニケーション能力を向上させ、人生の質を高めることができる。本書は、知覚の技法をマスターし、より良い人生を歩みたいと願うすべての人にとって、必読の書であると言えるだろう。
詳細目次
始まり
第一部 観 察
第一章 レオナルド・ダ・ヴィンチの力の秘密──大事なものを見る
第二章 名探偵、参上──観察の技をマスターする
第三章 カモノハシと泥棒紳士──どうして人によって見え方がちがうのか
第四章 客室乗務員が無意識に行なうこと──客観的観察のポイント
第五章 マヨネーズはどこに?──全体も細部も見る
第二部 分 析
第六章 全周に目を配れ──あらゆる角度から分析する
第七章 私はなぜ、引き金を引いたのか──情報の優先順位
第三部 伝 達
第八章 ワインの値段──コミュニケーションの不具合を防ぐ方法
第九章 ビッグ・スー──厳しい現実を適切に伝えるには
第四部 応 用
第一〇章 介護施設でストリップショー──生まれ持ったバイアスを克服する
第一一章 担架がないときはどうするか──不確かな状況に対応する方法
終わりに──知覚の技法をマスターする
謝 辞
著者より