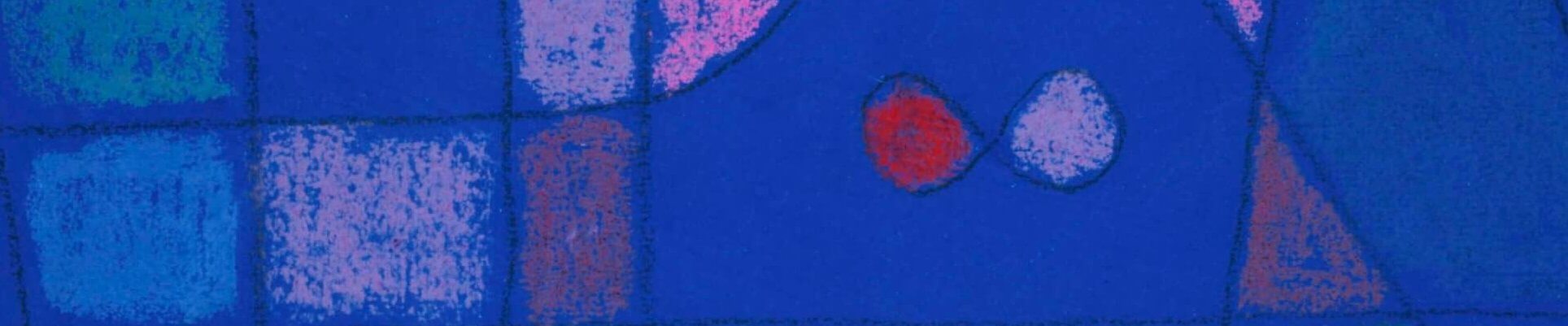「かくも長き不在」のご挨拶
羽田空港から淡路町への移転の中での「かくも長き不在」
羽田空港の法律事務所を後にしたのが2月末。3月いっぱいは、移転したカクイ法律事務所での片付けと仕事の態勢づくりに追われ、さて4月になったので、これから新しい ...
音声入力で文章を作成する(暫定版)
昔からあまりブラインドタッチが得意でなかった(ミスタッチが多くどうしてもキーボードを見てしまう)ので、時々、思い立ったようにパソコン用の音声入力専用ソフトを買ってきて音声入力を試みていた。
しかし最初に何十分も自分の声 ...
一難去って又三難
前回の投稿が、5月26日の「さわやかな初夏のお出かけ」だから、あっという間に2ヶ月が経ち、盛夏になってしまった。投稿する度に間が空いたことの言い訳をするのもみっともないが、それにしても私に降りかかるWOL(私が関与している会 ...
4月になって
「とにかくめまぐるしい40日でした」という投稿記事が3月2日付け、今日が4月3日なので、それからまるまる1ヶ月が経過したわけだ。
幸いなことに、会社は3月末に必要とされた多額な資金調達も何とか乗り切ることができて、羽田 ...
日本生産性本部の記念シンポジウム「2025年を見据えた生産性運動の進路」
昨日(2015年3月2日)、日本生産性本部が、「生産性運動60周年」を記念し、標題のシンポを開催した。記録として残されるかどうか知らないが、備忘のために、取り急ぎ印象に残ったことだけを記述しておく(ただ手許にメモ帳も ...
WordPressの記事のマークアップとCSSの備忘録
Wordpressは「テーマ」があるお陰で、ホームページ全体のレイアウトや、メニューの作成に全く力を注ぐ必要がなくなったので、作成者は記事を書いてエディターに貼り付けて「公開」すればいいだけだ。ただ、ホームペ ...
KindleのWord Wiseーこれで洋書が読めるか?
2014年12月7日の夜、Kindle Paperwhiteで本を読んでいたら、いきなりアップデートが始まった。よくあることなので気にしないでいたら、今回はなぜかずいぶん時間がかかる。終了後に再起動されると、W ...
WordPress備忘録
この記事は、このWEBが乗っている「WordPress」とその動かし方についての備忘録です。昔から思っていることですが、IT関係の知識は、「熱しやすく冷めやすい」知識の典型例で、どこかにまとめておかないとすぐに散 ...
「北杜の魅力再発見~大切じゃんね!!自然と風景~」を聞く
2014年11月29日(土)、北杜市の須玉で開かれた「北杜の魅力再発見」という催しを聞きに行った。
内容は、「南アルプスのエコパーク登録と北杜の自然」(輿水達司山梨県立大学特任教授)、「美しい風景を考え ...
ウインドウズ8とKINDLE本再論
「同時併行的ITパニック」という記事の中でウインドウズ8のことを少し賞賛した。ただ新しく買う場合はともかく、ウインドウズ7以前のウインドウズから、すぐにアップグレードすることはよく考えた方がいい。
ま ...