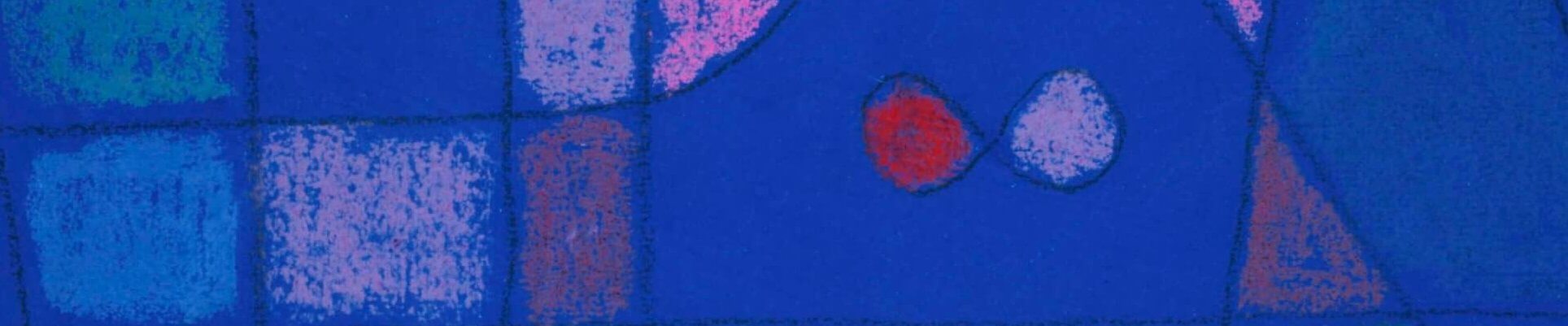この論稿の内容
この論稿は「予防訴訟と仮救済制度が問題となった事件」ということで執筆したものであるが、行政訴訟において問題となるどの訴訟類型を選択すればいいのかという「訴訟類型の選択」について網羅的に検討したものとなっているので、参考になると思い、掲載する。現時点では、まだほとんど元の原稿のままであるが、「訴訟類型の選択」ー裁判所に却下させないためにどのような訴訟を提起すべきかということに焦点をあてた論稿にすべく、適宜手を入れていきたい。
Ⅰ 予防訴訟と仮救済制度の概要
⑴本章で取り上げる「予防訴訟と仮救済制度」は、「行政庁の処分その他公権力の行使」(以下、「行政処分」ないし「処分」ということがある。)により、あるいは行政処分ではないが行政庁(以下、「行政機関」ないし「行政」ということがある)の行為が関わることにより発生する、国民の不利益ないし被害・損害を(恒久的に、あるいは暫定的に)予防し、現状を維持する手続であるという共通点がある。
⑵「予防訴訟」は一般的な概念であり、その範囲が明確なわけではないが、「差止めの訴え」(行訴3条7項。以下「差止訴訟」という)が中心的に検討され、「(非申請型)義務付けの訴え」(行訴3条6項1号。以下「(非申請型)義務付け訴訟」という)、「無効等確認の訴え」(行訴3条4項。以下「無効等確認訴訟」という)、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」(行訴4条後段。以下「実質的当事者訴訟」という)等も予防訴訟に含めて考えることができる場合があるし、民事上の差止請求も予防訴訟の機能を有する。
⑶また、「仮の救済」(以下「仮救済制度」という)は、取消訴訟等についての「執行停止」(行訴25条、26条)、差止訴訟についての「仮の差止め」(行訴37条の5)、義務付け訴訟についての「仮の義務付け」(同)である。実質的当事者訴訟については、後述するように民事保全法上の仮処分が利用できると解すべきである。
⑷本章で検討する、予防訴訟、仮救済制度は、いずれも平成16年の行政訴訟法の改正(以下「平成16年改正」という)において、国民の権利利益のより実効的な救済手段を確保するために新設ないし整備された規定であり、その立法趣旨の実現を目指すという観点から検討することが重要である
行訴附則50条の「法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加える」を踏まえ、平成22年12月から24年1月にかけて「改正行政事件訴訟法施行状況検証研究会」(以下、「検証研究会」という)が開催され(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00037.htmlにその配布資料、議事録が掲載されている)、その内容をまとめた「改正行政事件訴訟法施行状況検証研究会報告書」(以下、「検証報告書」という。http://www.moj.go.jp/content/000104214.pdf)が公表されているので、必要に応じて、これを参照する(検証研究会で検討された論点については、これに参加した深澤龍一郎教授の「改正行政事件訴訟法施行状況検証研究会の論点」(「論及ジュリスト8号」64~70頁)に要領よくまとめられている)。
⑸以下本章では、法文から明らかな裁判手続やその効力に関する記述は概説書に譲り、「問題点」のみ取り上げることとする。
Ⅱ 仮救済制度と執行停止
1 仮救済制度の概要
(1)仮救済制度についての平成16年改正
平成16年改正前の行政事件訴訟法で認められていた仮救済制度は、取消訴訟、無効等確認訴訟を提訴した場合に当該行政処分の効力等の停止を求める執行停止だけであった。しかし執行停止が認められる事案は多くはなかった。また、いわゆる授益的行政処分が拒否された場合に取消訴訟を提起しても執行停止制度は機能しないし(拒否処分が執行停止されても、授益的行政処分がなされる状態になるわけではないし、行政庁に再度の審査義務が生じるわけでもない)、仮処分も利用できないので、この場合、国民の権利救済の方法がないという大きな問題点があった。そこで平成16年改正法は、拒否処分に対して、義務付け訴訟が提起できることとし、その場合の仮救済制度として仮の義務付けが規定された。
また執行停止制度についても、その積極要件が「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」から、「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」(以下「重損要件」という)に改められた。
さらに差止訴訟が法定され、仮救済制度として仮の差止めが規定された。
⑵仮救済制度の概要
ア 行政事件訴訟法における仮救済制度は、次の【表1】のとおりである。
【表1】
|
本案訴訟
|
仮救済制度
|
条文
(行訴法)
|
|
|
行政処分前
|
行政処分後
|
|
|
抗告訴訟
|
取消訴訟
|
-
|
執行停止
|
25条、29条
|
|
|
無効等確認の訴え
|
-
|
執行停止
|
38条3項
|
|
|
不作為の違法確認の訴え
|
規定なし
|
-
|
-
|
|
|
義務付けの訴え
|
仮の義務付け
|
-
|
37条の5
|
|
|
差止めの訴え
|
仮の差止め
|
-
|
37条の5
|
|
|
当事者訴訟
|
執行停止の準用なし、仮処分
|
7条
|
|
|
争点訴訟
|
執行停止の準用なし、仮処分
|
7条
|
|
|
民衆訴訟・機関訴訟
|
43条2項の場合以外は執行停止の準用なし
|
43条2項
|
|
| |
イ 仮救済制度の、本案訴訟、根拠条文、準用条文は、次の【表2】のとおりである。仮救済制度については、すべて適法な本案訴訟の提起、係属が前提となっており、しかも裁判所は申立てがあって初めて判断できるものであって、職権ではできない(行訴25条2項、37条の5第1項・2項)。
また、仮救済制度には、内閣総理大臣の異議制度が定められている(行訴27条、37条の5第4項)。これは最近では、ほとんど利用されないが、予防訴訟等において利用されることがあれば、その妥当性の問題が再燃する可能性はあるだろう。
【表2】
|
仮救済制度
|
本案訴訟
|
根拠条文
|
準用条文
|
|
|
執行停止
|
処分の取消しの訴え
|
25条~28条
|
|
|
|
32条2項
|
32条1項
|
|
|
33条4項
|
33条1項
|
|
|
裁決の取消しの訴え
|
29条
|
25条~28条
|
|
|
無効等確認の訴え
|
38条3項
|
25条~29条、
32条2項
|
|
|
仮の義務付け
|
義務付けの訴え
|
37条の5第1項、3項~5項
|
25条5項~8項、
26条~28条、
33条1項
|
|
| |
|
仮の差止め
|
差止めの訴え
|
37条の5第2項~4項
|
|
次項では、執行停止を取り上げ、仮の差止め、仮の義務付けは本案訴訟と併せ、第Ⅲ項で検討する。
2 執行停止
(1)執行停止とは
ア 執行停止とは、取消訴訟や無効等確認の訴えが提起されても、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」(行訴25条1項))ことから、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をする」制度である(行訴25条1項・2項、29条、38条3項)。
上記の重損要件を「判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質および程度並びに処分の内容および性質をも勘案する(考慮事項。行訴25条3項)。消極要件として「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき(行訴25条4項)、本案について理由がないとみえるとき(同)」が規定されている。
処分の効力の停止が最も広い概念であり、処分の執行や手続の続行は、その一部と解されている。したがって、「処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない」(行訴25条2項ただし書)。
イ 執行停止の具体的な事案として、処分の対象である本人がする場合として、建築物の除却処分、懲戒処分(公務員、弁護士)、退去強制処分(強制送還部分、収容部分)、許可取消処分(公共施設利用許可)、免許や指定の取消処分(運転免許、医師免許、保険医登録、保険医療機関指定、介護保険法上のサービス事業者指定)、営業許可停止処分(風俗営業法、海上運送法上の許可等)等、第三者に対する処分についてする場合として、建築確認、産業廃棄物処理施設の許可処分、情報公開法に基づく開示決定)、保育園の指定管理者指定処分等が考えられる(大橋洋一「行政法Ⅱ 現代行政救済論」296、297頁)。
⑵執行停止に関する裁判例・問題点の検討
ア 検証研究会における配付資料によれば、平成16年改正以降、毎年執行停止は年間約200件程度申し立てられ、そのうち、約3分の1ないし半数が認容されているとされる。これは新受件数、認容件数とも上向いているが、改正前からさほど増加しているわけではないようであり、その後もほぼ同様の傾向にあるものと思われる。検証報告書に、認容事案、却下事案が紹介されているので参照されたい。検証研究会では、裁判所の運用について、重損要件が認められると思われるのに否定された事案がある、重損要件はなお過大な負担を申立人に強いているのでこれを軽減すべきである、第三者の損害がこれに含まれることが曖昧である、等の指摘がなされている。
イ 重損要件、及びその考慮事項である「重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする」という要件について、どのように理解し、裁判において、主張、立証すべきか。
平成16年改正前の「回復の困難な損害」についても、原状回復不能または金銭賠償不能な損害のみではなく、金銭賠償が可能であっても、その損害の性質・態様などから、社会通念上金銭賠償だけでは損害が補填されないと解釈される著しい損害も含むと解されてはいたが、結局、後で金銭的補償を受けることによって償えるかどうかという「性質」判断に大きく影響されていたというのが実際であった。
平成16年改正法は、積極要件を、「回復の困難な損害」という損害の絶対的「性質」から、「重大な損害」という比較が可能な損害の相対的な「量」に改めることにより、解釈の柔軟性を増そうとしたといえる。更に平成16年改正法で新しくつけ加えられた考慮事項が、「損害の性質および程度」のみではなく、「当該処分の内容および性質」をも勘案することとしたことにより、損害についてその回復の困難の程度が著しいとまでは認められない場合であっても、具体的な処分の内容および性質をも勘案したうえで、損害の程度を勘案して「重大な損害」が生じると認められるときは、執行停止を認めることができると解されている(小林久起「行政事件訴訟法」279頁)。
たとえば、情報開示決定によって不利益を受ける第三者が取消訴訟を提起しても、本案訴訟の間に開示されてしまえば、開示決定を取り消す利益は失われ、事後的な損害賠償によってその不利益を完全に償うことは困難であるので、「回復の困難な損害を避けるための緊急の必要がある」として執行停止が認められるべきであろう。地方議会議員の除名処分や弁護士の業務停止処分、除名処分等も同じことがいえる。
また事業者の営業停止処分について、営業が完全に破綻するとまでは認められないとしても、営業が悪化して重大な影響が生ずるおそれがあり、通常の営業に回復するまでに重大な損害が起こり得るというような場合においては、このような損害の回復の困難の程度や損害の程度をも考慮に入れ、事案の実情に即して執行停止が認められるべき場合もあろう。
さらに考慮事項について、損害の性質だけでなく当該処分がその内容および性質において申立人に与える影響のみならず、当該処分が広く多数の者の権利義務に対してどのような影響を与えるものであるかどうかなどを含めて、全体的な比較衡量をしたうえで当該処分の執行を停止することによる影響を適切に考慮しようとしたものであることも指摘されている(小林・前掲・280頁)。なお「緊急の必要があるとき」は、「重大な損害」の別の要件ではなく、両者は一体ないしその一要素であると解されている。
ウ 「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」との消極要件は、これまで、デモ行進、公共施設での集会、土地収用等で適用が認められたことがあるだけで、通常は、適用されることが少ない要件である。実際には、「重大な損害」や「本案について理由がないとみえる」に吸収されて判断されるといえる。
「本案について理由がないとみえる」か否かの判断は、事案の性質によって異なる。執行停止を認めることによって申立人が本案でも勝訴したのと同じ結果を得ることになる場合には、そうでない場合に比べて、より慎重に判断されることになろう。しかし、これは「理由があるとみえる」という積極要件ではなく、あくまで「理由がないとみえる」という消極要件であり、主張・疎明の責任は、行政機関にある。
Ⅲ 差止訴訟、非申請型義務付け訴訟、当事者訴訟及びその仮救済制度
1 予防訴訟における各訴訟の位置付け
差止訴訟等が新設された平成16年改正前にも、行政処分がなされる前に、その行政処分がなされること自体を差し止める無名抗告訴訟としての「予防訴訟(予防的不作為訴訟)」の活用が議論され、実際にそのような訴訟が提起されたこともあった(数は少ないが、差止めが認容された裁判例もあった)。平成16年改正法は、このような予防訴訟の機能に着目し、新たに行政処分がされることの予防を求める差止訴訟を法定した(行訴37条の4)。なお行政処分を差し止めるのとは逆に、行政処分を求めるのが、義務付け訴訟(同37条の2項、3)であり、これも平成16年改正法で新設された。義務付け訴訟のうち非申請型、更に成16年改正法で「公法上の法律関係に関する確認の訴え」が確認的に付加された実質的当事者訴訟も、予防訴訟として機能する場合があると考えられるので、本項で簡単に検討する。
これらが予防訴訟の類型ではあるが、そのすべてを網羅したものではなく、無名抗告訴訟としての予防訴訟もあり得る。しかし、まずは、これらについてその実効性と限界を検討し、これらによっては対処できない場合に、無名抗告訴訟としての予防訴訟が検討されるべきことになろう。
以下、差止訴訟(3項)、非申請型義務付け訴訟(4項)、仮の差止と仮の義務付け(5項)、実質的当事者訴訟と仮処分(6項)について検討する。
なお次項において、差止訴訟、非申請型義務付け訴訟、仮の差止と仮の義務付けの要件をまとめた。更に当然ではあるが、最も重要なのは、本案勝訴要件であることを確認する。
2 差止訴訟、非申請型義務付け訴訟及びその仮救済制度の要件の概要
⑴要件の概要
も止訴訟、非申請型義務付け訴訟及びその仮救済制度の訴訟要件等をまとめると、以下の【表3】のとおりである。
|
訴訟類型
(仮の救済の類型)
|
訴訟要件
(積極要件)
|
考慮事項
|
本案勝訴要件
(消極要件)
|
|
差止めの訴え
|
ⅰ 一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあること。
ⅱ ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときはこの限りでない(行訴37条の4第1項)
ⅲ 行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であること(行訴37条の4第3項)
ⅳ 処分または裁決がなされる蓋然性があること
|
重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案する(行訴37条の4第2項)
|
・行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるとき(行訴37条の4第5項)
・行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき(同)
|
|
仮の差止め
|
ⅰ 差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき(行訴37条の5第2項)
ⅱ 本案について理由があるとみえるとき(行訴37条の5第2項)
|
|
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき(行訴37条の5第3項)
|
|
(非申請型)
義務付けの訴え
|
ⅰ 一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること(行訴37条の2第1項)
ⅱ その損害を避けるため他に適当な方法がないとき(同)
ⅲ 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者であること(行訴37条の2第3項)
|
重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案する(行訴37条の2第2項)
|
・行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるとき(行訴37条の2第5項)
・行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき(同)
|
|
仮の義務付け
|
ⅰ 義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき(行訴37条の5第1項)
ⅱ 本案について理由があるとみえるとき(同)
|
|
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき(行訴37条の5第3項)
|
|
執行停止
|
処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき(行訴25条2項)
|
重大な損害を生ずるか否かを判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質および程度並びに処分の内容および性質をも勘案する(行訴25条3項)
|
ⅰ 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき(行訴25条4項)
ⅱ 本案について理由がないとみえるとき(同)
|
⑵最も重要な要件は何か
ア 差止訴訟にせよ、非申請型義務付け訴訟にせよ、最も重要なことは、本案訴訟において勝訴すること、すなわち本案勝訴要件の充足である(仮の差止めや仮の義務付けが認められるためにも「本案について理由があるとみえる」ことが必要である)。
そして、本案勝訴要件は、覊束処分の場合は「行政庁がその処分をすべきであること、又はすべきでないことの処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるとき」である。
裁量処分の場合は「行政庁がその処分をしないことが又はその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」である。
なお、本案勝訴要件は判決の要件であるから、遅くとも事実審の口頭弁論終結の時点で、そのような状態にあると認められる必要がある。
前者は限られた場合しか考えられないだろうから、本案勝訴のために重要なのは、後者の裁量処分について、行政機関が、一定の処分」をすること若しくはしないことが、「裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」が主張、立証できるか否かだと考えられる。
訴訟要件は本案判断の前提に過ぎず、本案勝訴要件が存在する(とみえる)のに、重損要件がないので却下されることは例外的な場合であろう(もちろん、裁判所はそのような順序では判断しないが)。そしてその場合であれば、「一定の処分」について、その後も、相応の争う手段があり得るだろう。
イ 訴訟提起にあたっては、差止訴訟や非申請型義務付け訴訟、取消訴訟、無効等確認訴訟、実質的当事者訴訟のそれぞれの本案勝訴要件を勘案し、どれが選択できどれであれば本案訴訟の勝訴に結び付くか、更に仮の救済を得ることが必要か否かを、選択・判断することになる。
3 差止訴訟
(1)差止訴訟とは
差止訴訟の具体的な事案として、処分の対象である本人がする場合として、公務員に対する懲戒処分、営業許可の取消処分、行政庁の規制・監督権限に基づく事業者への制裁処分の公表等が、第三者に対する処分についてする場合として、建築確認や廃棄物処理施設の設置許可、情報公開制度による開示決定等が考えられる。
「公権力の行使による侵害を未然に防ぐという意味において、差止訴訟は法治国家原理に結合が容易であるという側面をもともと持っているとともに、処分に先行して、制定法上に公表、回答などの法的しくみが活用されていること、現代の情報社会の下では、規制的処分の波及効果が大きいことから、その必要性が増している」(塩野宏「行政法Ⅱ〔第5版〕」*頁))として、国民の権利利益の救済のために、差止訴訟が重要な役割を担うことが指摘されている。
⑵ 差止訴訟に関する問題点・裁判例等の検討
ア 本案勝訴要件と訴訟要件について簡単に検討する。
本案勝訴要件は、上述したとおりであるが、本案訴訟が最終的に認容された事案は多くはなく、タクシーの運賃関係の事案、「鞆の浦事件」(百選)が見当たるぐらいである。
イ 訴訟要件全般については、第Ⅳ項1⑶で検討する「日の丸・君が代訴訟」が重要である。
(ア)訴訟要件のうち「一定の処分」は、裁判所の判断が可能な程度に特定される必要があるが、一義的に確定している必要はない(「」東京地判:平成20年1月29日判時2000号27頁)は疑問である。なお、差止訴訟においては、民事訴訟であれば認められる(「一定の処分又は裁決」によって生じた)結果の差止めは認められず、その結果の原因となる「一定の処分又は裁決」の差止めを求めなければならない。
(イ)訴訟要件のうち重損要件が争点になることも多い。行政処分後に取消訴訟を提起し、執行停止を申し立てるルートもあるのだから、重損要件は、それでは十分な救済が得られない場合に、当該処分の差止めが認められるための要件だとされる。
一見分かりやすい説明だし、両ルートの選択についてのメルクマールが必要なのは当然であるが、差止訴訟は、「一定の処分」についての本案勝訴要件(裁量権の範囲を超え若しくはその濫用)+重損要件+(仮の差止め)のルート、取消訴訟は、過去の具体的な処分についての本案勝訴要件(違法性)+執行停止(重損要件)のルートだから、差止訴訟の重損要件が直ちにそのような機能を有しているとはいえない。
問題は「一定の処分」がなされる蓋然性がある(その蓋然性にも幅がある)ことを前提として、想定される処分がどこまで切迫していて具体的か、その処分後にする違法性判断と救済は容易か、その処分を取り消すというのが現実的か等を勘案し、本案勝訴要件(裁量権の範囲を超え若しくはその濫用)に踏み込んで判断することが妥当か否かを見極めることが、重損要件とその考慮事項に期待されることであろう。
例えば第Ⅳ項で検討する「第4次厚木基地訴訟」における自衛隊機の運航が将来の処分であるとしてもその取消しはそもそも想定しがたいから、容易に重損要件が認められる。
一方、「君が代・日の丸訴訟」では、「懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされる危険が現に存在する状況の下では、懲戒処分の消訴訟等の判決確定に至るまでに相応の期間を要している間に、懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされていくと事後的な損害の回復が著しく困難になる」からとして重損要件を認めた。
エ 但し書きの「補充性」は、法令上、先行する処分の取消訴訟を提起すれば、後続の処分を争うことができないという特別の手続上のしくみが定められているような場合と解される。個別法において一定の処分を猶予する特別の救済手段を定めているので消極要件に該当する場合として、国税徴収法90条3項、国家公務員法108条の3第8項、地方公務員法53条8項等があげられている。したがって、民事訴訟による差止請求が可能であるとか、実質的当事者訴訟が可能であることから、消極要件に該当するとはいえない。
4 非申請型義務付け訴訟
(1)義務付け訴訟とは(2類型)
ア 義務付け訴訟は、「行政庁が処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟」であり、非申請型義務付け訴訟(一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がない場合。行訴3条6項第1号。)と、申請型義務付け訴訟(法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない場合。行訴3条6項第2号)で、「当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと」(不作為型。行訴37条の3第1項1号)、又は、「法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在である場合」(拒否処分型。行訴37条の3第1項2号)がある。
実際に多く利用されるのは、申請型義務付け訴訟であるが、ここでは、予防訴訟として非申請型義務付け訴訟を検討する。
イ 非申請型義務付け訴訟のうち、自分に対して職権発動をして行政処分をすることを義務付ける訴訟もあり得るが(在留特別許可の義務付け等が該当するであろう)、第三者に対する規制権限の発動を求める訴訟が典型である。例えば、行政機関に対し、産業廃棄物処理場の周辺住民が産業廃棄物の処分について代執行ないし措置命令を命ずること、原子炉周辺の住民がこれを設置管理している電力会社へ運転停止命令を出すこと、周辺住民が違法建築物について是正命令を出すことを求めること等が、非申請型義務付け訴訟である。第Ⅳ項で検討する「大阪空港騒音差止訴訟」は、離着陸の禁止を行政機関に求める非申請型義務付け訴訟に該当すると解されよう。
(2)非申請型義務付け訴訟に関する問題点・裁判例の検討
検証報告書を見ると、非申請型義務付け訴訟の認容事例として、産業廃棄物施設の設置許可処分を取り消すことや措置命令を求めた具義務付け訴訟が認容された事例があるぐらいである。その後も目立った事例はない。問題はやはり本案勝訴要件である「行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」を認めさせるのがなかなか困難であるということである。
行政機関を相手方に非申請型義務付け訴訟をするのがよいのか、民間事業者を相手に民事差止請求をするのがより良いのかという問題である。
5 仮の差止め・仮の義務付け
⑴ 仮の差止め、仮の義務付けの積極要件、解釈規定、消極要件は、上記したとおりである。また仮仮の差止め・の義務付けの裁判の手続と効力については、執行停止の規定が準用されている(行訴37条の4。31条1項は準用されていない)。
⑵仮の義務付け・仮の差止めに関する裁判例・問題点の検討
ア 積極要件、その他
仮の差止め・仮の義務付けの、一つ目の積極要件は、「償うことのできない損害」である。
差止訴訟、非申請型義務付け訴訟の積極要件は、重損要件であるが、仮の差止め・仮の義務付けは、本案判決の前に、裁判所が、行政庁が仮に具体的な処分をすべきことまたはすべきでないことを命ずる裁判であり、本案訴訟の結果と同じ内容を、仮に実現するものであるから、より厳格な要件を規定していると考えられる。したがって、「償うことのできない損害」とは、「重大な損害」よりも、損害の回復の困難の程度が比較的著しい場合をいうものと考えられよう。
どのような場合が「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」がある場合に該当するかは、裁判所が、個別具体的な事情に即して判断すべきことであるが、「償うことのできない損害」といっても、金銭賠償が可能であれば除かれるものではなく、社会通念に照らして金銭賠償のみによることが著しく不相当と認められるような場合を含むものと考えられよう。
「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」がある場合として具体的に想定される事例としては、たとえば、①仮の差止めであれば、本案判決が確定するまでの間に営業停止などの制裁処分が公表されて信用が害される場合、②仮の義務付けであれば、年金や公的保険などの資格認定やその給付が、本案判決が確定するまでの間の生活の維持に必要不可欠である場合などが考えられる。
このような場合に、仮の救済の必要性という観点から、事業活動や生活の基盤に深刻な影響を及ぼすおそれがあるかどうか、回復が著しく困難な状況を生じさせるおそれがあるかどうかなど、それぞれの事案に応じて様々な事情を考慮したうえで、「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるか否かを判断することになる。
二つ目の積極要件として、申立てを認める決定は、いずれも、「本案について理由があるとみえるとき」にすることができるとされている。この点、執行停止は、「本案について理由がないとみえるときは、することができない」と消極要件とされているが、仮の義務付けまたは仮の差止めの決定をするには、本案について理由があると一応認められる必要がある。
「本案について理由があるとみえるとき」とは、本案訴訟である義務付けの訴えまたは差止訴訟に関して主張する事実が、法律上、その判決をする理由となる事情に該当すると一応認められ、かつ、その主張する事実が一応認められる場合と考えられよう。
仮の義務付けについて、検証報告書には、障害をもつ子供について町立幼稚園への入園を仮に義務付けた徳島地方裁判所の決定(徳島地決平成17・6・7最高裁ウェブサイト)、をはじめとして、生活保護、入園・入学等について10件弱の認容事例が掲戴されている。このような申請型義務付けの場合は比較的活用されているようである。
しかし非申請型の仮の義務付けや、仮の差止めについては、本案訴訟の認容事例自体がほとんどないこともあって、認容事例もほとんどない。
6 実質的当事者訴訟と仮処分
⑴当事者訴訟
取消訴訟の対象である「行政庁の処分その他公権力の行使」ではない行政機関の行為を契機として争いが生じた場合に権利救済を求めるには、「公法上の法律関係に関する訴訟」(実質的当事者訴訟:行訴4条後段)を提起することが可能である。
これには、①処分ではない行政の行為についての、(a) 処分ではない行為の無効を前提として公法上の権利義務を争う訴訟、(b) 処分ではない行為に対する訴訟、②公法上の権利義務を争う訴訟、③処分の無効を前提に公法上の権利義務を争う訴訟の3類型があると指摘されている(大橋洋一「行政法Ⅱ」272頁)。
➀(a)として、例えば、政令・省令などの行政立法、条例などの自治立法、省令に基づく公示、通達、行政計画等について、そこから生じる負担や義務がないことの法律上の地位の確認を求める場合が挙げられる。なお処分ではない行政の行為そのものを訴訟の対象とするのが適切な場合に認められるのが、①(b)である。これらは、平成16年改正で行訴4条に付加された「公法上の法律関係に関する確認の訴え」の活用として考えられるべきものである。後述する「君が代・日の丸訴訟」の「処分以外の不利益措置」を予防するために「起立・斉唱・伴奏」義務がないことを求める確認訴訟が、これに該当することが認められた。
➁は、伝統的に公法上の法律関係とされてきた社会保険、社会保障、公務員・議員の法律関係に関する訴訟である。
③は抗告訴訟である無効等確認訴訟の利用が制限される場合(行訴36条)である。
実質的当事者訴訟として、「薬事法改正違憲判決」「在外国民選挙権訴訟」(百選Ⅱ)、「国籍法違憲判決」、「医薬品ネット販売規制違憲判決」等の存在活用が指摘されており(櫻井敬子「行政救済法のエッセンス」185~189頁)、今後もその活用が期待され。
⑵仮処分の利用
行政事件訴訟法44条は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に「仮処分をすることができない」としているが、これについて「公権力の行使」が関係する場合は広く「仮処分」が排除されるとの見解があった。しかし、行政事件訴訟法44条は、行政事件訴訟法が仮処分とは別の仮救済制度を用意している抗告訴訟(公権力の行使に関する不服の訴訟)において仮処分の利用を排除している規定であると理解すれば十分である。検証報告会でも「公法上の法律関係の争いについては、公権力の行使に当たる行為であれば執行停止等の仮の救済を利用することになり、他方で、それ以外のものについては行政事件訴訟法7条により民事仮処分を利用すること」(検証研究会報告書)と理解されている。
Ⅳ 予防訴訟における訴訟類型の選択についての諸問題
1 訴訟類型の選択の困難さ
(1)現在の行政訴訟制度については様々な評価があるだろうが、その大きな問題点として、原告適格、訴えの利益、行政処分の範囲の曖昧さ、難解さ、更には「法律上の争訟」ではないとの切り捨て(「宝塚市パチンコ条例事件」(百選Ⅰ-109事件)等と並んで、どういう訴訟で争うかという訴訟類型の選択の困難さという問題があることに異論はないであろう。
特に予防訴訟については、本案の内容よりも、それに先立つ訴訟類型の選択とその適法性の問題が大きな論点となってきた。せっかく本案の内容について詳細な主張、立証を展開しても、当該訴訟類型を選択したことが不適法であるとして却下されるのでは、それまでの訴訟追行の努力のすべてが無に帰してしまう。しかし実際は、行政訴訟では、単純かつ典型的な取消訴訟以外では、そのような事態が頻発してきたのである。そのため、予防訴訟に限らず、典型的な取消訴訟に該当するとはいえない場合に、行政機関の行為を争おうとする国民側の訴訟代理人は、訴訟類型を網羅した請求の趣旨を掲げて、行政側代理人の執拗な「却下」攻撃と、それに同調しがちな裁判所と闘わざるを得なかったのである。
ただそれは、以下検討する「日の丸・君が代訴訟」や「第4次厚木基地訴訟」における最高裁判決によって、ある程度整理されたととらえることができる。
⑵公共施設の設置・供用の瑕疵をめぐる訴訟
ア ここで予防訴訟の典型と考えられる公共施設の設置・供用の瑕疵を争う訴訟についての、訴訟類型の選択の問題について検討してみよう。
この問題を検討するときは、設置・供用主体が、行政機関か民間か、設置・供用に先行する行政機関の行為が処分性を有するか否か、設置・供用の瑕疵について将来的に行政の「一定の処分」が考えられるか否かで異なった検討することになる。細かい点は措き、私見によれば現時点での実務的な扱いを抽象的にまとめれば、次の【表4】のとおりである。なお訴訟類型の説明については、後記【表5】を参照されたい。
【表4】
|
番号
|
主体
|
先行行為の処分性の有無
|
「一定の処分」の有無
|
訴訟類型
|
事案
|
|
1
|
行政
|
〇
|
〇
|
取消・無効確認、差止・義務付け
|
第4次厚木基地
|
|
2
|
✕
|
取消・無効確認
|
|
|
3
|
✕
|
〇
|
当事者、差止・義務付け
|
大阪空港騒音
|
|
4
|
✕
|
当事者、民事差止
|
ゴミ焼却場設置
|
|
5
|
民間
|
〇
|
〇
|
取消・無効確認、差止・義務付け、民事差止
|
原子炉設置
|
|
6
|
✕
|
取消・無効確認、民事差止
|
|
|
7
|
✕
|
〇
|
差止・義務付け、民事差止
|
|
|
8
|
✕
|
民事差止
|
|
イ まず公共施設の設置・供用の根拠となる先行する行政機関の行為の処分性について、「判例は、行政の一連の行為を一体的に把握して処分性を論じるのではなく、個々の法的行為に分解して分析する方法をとっている。その結果、公共施設の設置や供用については、処分性が否定され、これに対する抗告訴訟は認められないが、民事差止訴訟が可能であると解されるから、救済に欠けることはない」(中原茂樹「基本行政法第3版」284頁)と指摘される(「大田区ゴミ焼却場設置差止訴訟」(最判昭和39年10月29日:百選)は、上記表4の4に該当しよう)。ただ民事差止訴訟の根拠は、人格権や環境権という抽象的な権利であることが多く、差止めが認容される要件も厳しいので、処分性が肯定され、取消訴訟や無効確認訴訟による争いの方が適切なこともある。
ウ 電力会社が運営する原子力発電所の原子炉の設置、運転については、周辺住民による原子炉設置許可処分に対する取消訴訟や無効確認訴訟と、民事上の差止訴訟が併存して認められてきている。「運転停止等に係る一定の処分」を命じる非申請型義務付け訴訟も認められよう(上記表4の5に該当する)。ただし本案についての判断で、行政訴訟、民事訴訟のどちらが争いやすく、目的を達成する可能性があるのかは、難問である。
エ 騒音被害をもたらす航空機の運航についての空港や基地供用の瑕疵
(ア)騒音被害をもたらす航空機の運航について、国営空港や自衛隊基地の供用の瑕疵について、どのような訴訟類型で争うべきなのかということが、長年にわたって争点となり、解決を見なかった。
このような事態を招いた元凶ともいうべき「犯人」が、国営空港の供用についての、最高裁の「大阪国際空港夜間飛行禁止等請求訴訟」(以下「大阪空港騒音差止訴訟」という)についての判決(最判昭和56年12月16日:百選Ⅱ※)であるといえる。
それまでは、国営空港に離発着する航空機騒音について民事訴訟による差止請求が不適法とは考えられていなかったのに、同判決は、大阪空港を「国営空港とした本旨」を強調した上で「本件空港の離着陸のためにする供用は運輸大臣の有する空港管理権と航空行政権という二種の権限の、総合的判断に基づいた不可分一体的な行使の結果であるとみるべきであるから、住民らの請求は、事理の当然として、不可避的に航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することとなるものといわなければならない。したがつて、住民らが行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして、国に対し、いわゆる通常の民事上の請求として前記のような私法上の給付請求権を有するとの主張の成立すべきいわれはないというほかはない。以上のとおりであるから、住民らの本件訴えのうち、いわゆる狭義の民事訴訟の手続により一定の時間帯につき本件空港を航空機の離着陸に使用させることの差止めを求める請求にかかる部分は、不適法というべきである」としたのである。
同判決による不意打ち的な判断、及び「行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして」などという無責任な物言いは、以後強く批判され、平成16年改正につながったといえよう。
しかしその後も、どのような要件があれば騒音被害をもたらす航空機の運航を差し止める訴訟が適法であるのかを顧慮することもなく、民事訴訟を却下し、一方、行政訴訟も却下する裁判例が相次いだ。
(イ)しかし最高裁は、自衛隊が設置する飛行場における自衛隊機の運航の差止めに係る「厚木基地第4次航空機運行差し止め訴訟」(最判平成28年12月8日:百選Ⅱ※)(以下「第4次厚木基地訴訟」という)で、「住民らの主張する自衛隊機の運航により生ずるおそれのある損害は、処分がされた後に取消訴訟等を提起することなどにより容易に救済を受けることができるものとはいえず、本件飛行場における自衛隊機の運航の内容、性質を勘案しても、住民らの自衛隊機に関する主位的請求(運航差止請求)に係る訴えについては、「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる」として、少なくても「防衛大臣の権限の行使」によって行われる自衛隊機の運航については、差止訴訟が適法であることを認めた。
(ウ)自衛隊機の運航の差止めが(少なくても)抗告訴訟によって可能なのに、国営空港における民間機の離発着について差止めの請求ができないというのでは、いかにも均衡を失する。
上記に当てはめれば、自衛隊機の運航の差止めは上記表4の1に、国営空港における離発着への供用の差止めは、上記表4の3に該当するから、それぞれ少なくても抗告訴訟(差止訴訟、非申請型義務付け訴訟)で争うことは適法である。しかし上記表4の1の場合はともかく、上記表4の3の場合に民事差止訴訟を不適法とすることは、なお疑問が残る。
⑶「日の丸・君が代訴訟」による訴訟類型の整理
ア 次に国民への処分、損害についての「予防訴訟」の訴訟類型が問題となった「東京都教職員国旗国歌訴訟」(最判平成24年2月9日:)百選Ⅱ※)(以下「日の丸・君が代訴訟」という)を検討する。
これは次のような事案であり、教職員らの本案訴訟は退けられたが、予防訴訟の訴訟類型の選択についての問題を詳細に判示し、これまで予防訴訟の提起にあたって却下を恐れ、網羅的に請求の趣旨を掲げざるをえなかった実務の混乱を、整理しようとしたものという限りで評価することができる。
「東京都教育委員会の教育長は、都立学校の各校長に対し、教職員に対して、入学式、卒業式等において国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、ピアノ伴奏をすること(以下「起立・斉唱・伴奏」という)を命ずるよう通達した(本件通達)。校長らはこれに従って、入学式や卒業式等の式典に際し、そのつど、教職員に対し、職務命令書によって個別に起立・斉唱・伴奏を命じている(本件職務命令)。教育長は、本件職務命令に従わなかった教職員に対し、1回目は戒告、2回目は減給1ヵ月、3回目は減給6ヵ月、4回目は停職1ヵ月という基準で懲戒処分を行っている。なお、過去に他の懲戒処分歴のある教職員に対しては、より重い処分がされているが、免職処分がされた例はない」。
イ まず最高裁は、本件通達と、本件職務命令が行政処分であることを否定した上で、次のような救済法方法があるから「争訟方法の観点から権利利益の救済の実効性に欠けるところがあるとはいえない」とした。行政処分であるか否かが明確なものであれば問題がないが、解釈が分かれる余地があるものは、なお訴訟選択の問題が残ることになる。
ウ 差止訴訟の適法性
最高裁は、ⅰ免職を除き「本件職務命令違反を理由とする停職、減給または戒告の懲戒処分」について「一定の処分」と認められる、ⅱ「本件通達を踏まえて懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされる危険が現に存在する状況の下では、事案の性質等のために(懲戒処分の)取消訴訟等の判決確定に至るまでに相応の期間を要している間に、毎年度2回以上の各式典を契機として……懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされていくと事後的な損害の回復が著しく困難になることを考慮すると、「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる、ⅲ補充性の要件を満たす、ⅳ処分の名宛人となるものが訴訟を提起しているので原告適格がある、として、差止訴訟が適法であるとした。
エ 本件職務命令による起立・斉唱・伴奏義務がないことの確認訴訟
(ア)これについては、「将来の処分の予防を目的とする場合」は、法定外抗告訴訟と認められるが、差止訴訟が可能なので、法定抗告訴訟との関係で事前救済の争訟方法としての補充性を欠き、他に適当な争訟方法があるものとして不適法である。
(イ)しかし「処分以外の不利益の予防を目的とする場合」は、「本件通達を踏まえて処遇上の不利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険が現に存在する状況の下では、毎年度2回以上の各式典を契機として上記のように処遇上の不利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大していくと事後的な損害の回復が著しく困難になることを考慮すると、本件職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を求める本件確認の訴えは、行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上の法律関係に関する確認の訴えとしては、その目的に即した有効適切な争訟方法であるということができ、確認の利益を肯定することができるものというべきである」。
以上の検討を踏まえ、予防訴訟における訴訟類型の選択について次項でまとめてみよう。
3 予防訴訟における訴訟類型の選択についてのまとめ
- 最後に予防訴訟において選択可能と考えられる訴訟類型をまとめると、下記【表5】」のとおりである。
【表5】
|
請求の対象
行政の行為
|
過去の行為
|
現在の法律関係
|
将来の法律関係
|
|
|
処分
|
➀取消訴訟
|
|
⑤(一定の処分の)差止訴訟
⑥(一定の処分の)義務付け訴訟
|
|
|
②無効等確認訴訟 ※1
|
③ ※2´
|
|
|
非処分
|
③実質的当事者訴訟
④民事訴訟
|
⑦民事訴訟
|
|
| |
| |
※1 行訴36条前段は「予防訴訟」と解される
※2 行訴36条後段の「現在の法律関係に関する訴え」や争点訴訟(民事訴訟)が考えられる
|
|
ア 法的紛争に関わる訴訟は、過去の行為そのものを対象とするのではなく、現在の法律関係に引き直して争うのが原則であるが、行政処分の法的効果を争うには、過去の行為である行政処分を取り消す訴訟によらなければならないとされ(①取消訴訟の排他的管轄)、行政処分以外についての紛争は、「実質的当事者訴訟」(③)によって争うものとして明確に区別されている。
イ 行政処分については上述した「大田区ゴミ焼却場設置訴訟」が判示した「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」が「定式」とされるが、これは、行政事件訴訟特例法の「処分」についての判断であり、行政事件訴訟法ではこれに「その他公権力の行使に当たる行為」が加えられた。これには上記「処分」に加えて、公権力的事実行為も含まれるが、その性質上継続性のない事実行為は取消訴訟の対象外であるとされた(「事例研究行政法」※頁)とされた。したがって継続性のない公権力的事実行為も、取消訴訟以外の抗告訴訟の対象となる。
ウ しかし、行政処分に「重大明白な瑕疵があって無効」な場合(多くは、取消訴訟の出訴期間が徒過した場合に問題となる)は、原則に戻って、無効な行政処分を前提とする「現在の法律関係に関する訴訟」である「実質的当事者訴訟」や民事訴訟である「争点訴訟」(③)※2)で争うこととなる。
しかし行政事件訴訟法は、これに加えて、過去の行政処分についての「無効等確認訴訟」(②)を認めたので、「実質的当事者訴訟」との関係が問題となる。これについて行訴36条は、「無効等確認の訴えは、(ⅰ該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者)(ⅱその他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、ⅲ当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り)、提起することができる」とした(なおⅲがⅰにもかかるのかという争いがあったが、ⅰと、ⅱ+ⅲが、それぞれ無効等確認訴訟の原告適格を定めているというのが判例の考え方とみられる)。
したがって36条後段(ⅱ+ⅲ)の要件を満たす場合には、 無効等確認訴訟を提起し、 それ以外の場合は、「実質的当事者訴訟」で争うという振分けがなされている。ここでⅲの「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」(補充性)という要件は、「実質的当事者訴訟」が利用できるだけでなく、無効等確認訴訟の方が、より直截的で適切な争訟形態であるという場合を含むと解されている。
なお36条前段は、「予防訴訟」を定めていると解されており、その例として、無効な建築物除却命令に基づく代執行を阻止するために提起される当該除却命令の無効等確認訴訟や、重大明白な瑕疵のある課税処分に基づいて滞納処分を受けるおそれがある者がする課税処分無効確認訴訟等が挙げられている。
なお「実質的当事者訴訟」の3類型について、Ⅲ6項で整理した。
エ 上記した「日の丸・君が代訴訟」にの最高裁判決が何を論じたかを確認すると、本件通達や本件職務命令には処分性がないので、これらの①取消訴訟はできない、しかし、将来、停職、減給、戒告の懲戒処分がなされる蓋然性がある等の⑤差止訴訟の訴訟要件を満たすので、差止訴訟は適法である(差止訴訟の本案勝訴要件(行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき)は認められない)。
本件職務命令による起立・斉唱・伴奏義務がないことの確認訴訟につき、「将来の処分の予防を目的とする確認訴訟」は、「無名抗告訴訟」であるが、⑤差止訴訟が認められるので不適法である、「処分以外の不利益の予防を目的とする確認訴訟」は④「実質的当事者訴訟」として適法であるが、本案勝訴要件である本件職務命令が違憲無効であって起立・斉唱・伴奏義務がないとはいえないとされた。